1967 年 8 月、国連マルタ代表団長のアルヴィド・パルド大使の提案から始まり、人類の共通の利益にかなう海底と海洋を規制する国際条約のアイデアが生まれました。 1973年、海洋の管理に関する包括的な国際条約を交渉するという使命を帯びて、第3回国連海洋法会議が正式に開催されました。 9年間の交渉を経て、1982年4月30日に130票賛成(反対4票、棄権17票)で1982年UNCLOS草案が採択された(1) 。署名開始当日(1982年12月10日)に117カ国が条約に署名した。 1982年の国連海洋法条約は、60か国の加盟国が批准した1年後の1994年11月16日に正式に発効しました。現在までに、1982年の国連海洋法条約は168の加盟国によって批准されている(2) 。

包括的かつ公正な法的枠組み
1982年のUNCLOSに先立ち、1958年に国連は第1回海洋法会議を開催し、領海及び接続水域、大陸棚、公海、漁業及び公海生物資源の保存に関する4つの条約と紛争解決に関する議定書を通じて、海洋問題を規制する最初の国際的な法的枠組みを実現しました(3) 。これは、沿岸国の相反する利益と国際社会の共通の利益を調和させ、海上で初の国際法秩序を確立するための大きな一歩です。しかし、1958年の条約では多くの限界が明らかになりました。
まず、各国が領海や漁業水域の幅について合意していないため、海洋境界の確定が完了していない。第二に、海における権利と利益の分割は、開発途上国や地理的に不利な国の利益を無視して、先進国の利益を保護する傾向がある(4) 。第三に、沿岸国の大陸棚限界を超える国際海底は、国際法規制によって規制されず、完全に開放されたままになっています。第4に、紛争解決議定書は国際司法裁判所(ICJ)を通じた強制的な解決の選択肢を狭めており、そのため広範な支持を得ていない(5) 。第五に、海洋環境の悪化や汚染の問題が予想されているにもかかわらず、海洋における海洋生物資源の保全に関する規制は、汚染源、汚染の範囲、海洋環境汚染違反に対する制裁の面で十分ではありません。
1982年の国連海洋法条約は、1958年の条約の限界を克服し、沿岸国と内陸国、あるいは地理的に不利な国と先進国と開発途上国や後進国など、異なるグループの国々の利益を調和させる公正な法的枠組みを構築しました。
具体的には、1982年に国連海洋法条約により初めて、内水、領海、接続水域、排他的経済水域、大陸棚、公海、亜海域(国際海底)から海域の境界を定める規定が完成しました。特に、排他的経済水域制度は、1960年代の民族解放運動の中で、発展途上国や新興独立国の経済的特権を保護する結果として誕生しました。これは、条約が誕生する以前から科学技術の発達した国々によって確立された伝統的かつ歴史的な漁業権に基づく規制を除き、200海里(6)以内の海洋生物資源の自然な分布を考慮し、すべての国に対する公平性を確立した初めての法的体制である。
大陸棚については、1982年の国連海洋法条約において、陸地が海を支配するという原則を尊重し、客観的な地理的基準に基づいて大陸棚の境界を定める基準が定められています。したがって、大陸棚は、沿岸国の本土領土の自然な延長である地質学的な概念です。したがって、各国が決定できる法的大陸棚の最小幅は、基線から 200 海里となります。 200海里以上の自然大陸棚を持つ国は、延長された法的大陸棚を定義することが認められている(7) 。しかし、公平性と客観性を確保するため、国連大陸棚限界委員会(CLCS) (8)が沿岸国の延長大陸棚の決定方法を検討する権限を持ち、同委員会の勧告に従って決定された延長大陸棚境界のみが拘束力を持ち、他国から承認を受けることになる。
排他的経済水域の制度に、余剰漁業の輸送と利用に関する一連の規制を盛り込む際には、内陸国や地理的に不利な国の利益も考慮される(9) 。さらに、群島国家の特性も初めて考慮され、群島国家の法的地位に法典化された(10) 。
特に、1982年の国連海洋法条約は、海洋の自由に関する規定を継承するとともに、人類共通の遺産としての性格を有する深海底地域の法的体制を初めて確立した。特に、海底機構(ISA)は、深海底資源の開発に関する規制を策定し、加盟国に利益を公平に分配するために設立されました(11) 。 1982年の国連海洋法条約に当該地域の管理と開発に関する特定の規定を補足するため、1994年には「第11部の実施に関する協定」も締結された。
海上紛争を解決するための平和的メカニズム
国連憲章は国際紛争の平和的解決の原則を規定しています。したがって、紛争は、交渉、調査、調停、和解、仲裁、裁判所、地域および国際機関などの措置、または当事者自身が選択したその他の平和的手段を通じて解決されなければならない(12) 。 1982年の国連海洋法条約は、この原則の精神を再確認するとともに、条約の解釈と適用に関する加盟国間の紛争の具体的な性質に適した紛争解決メカニズムを創設するために平和的手段を巧みに取り入れました。
したがって、1982 年の UNCLOS では、当事者が以前に合意した紛争解決措置に関する合意が優先されます。 1982年の国連海洋法条約では、紛争解決に関する事前の合意がない場合には、強制的な措置として意見交換の規定を通じて当事者が直接交渉することを義務付けています。さらに、1982 年の UNCLOS では、直接交渉を促進するために、当事者が自発的な選択肢として調停を利用することを奨励しています。
しかし、強制的な意見交換はいつまでも有効というわけではありません。条約は、締約国に対し、合理的な期間内に意見を交換する義務を負うことのみを規定している(13) 。その期間が経過しても、当事者間で紛争を解決するための解決策が見つからない場合は、裁判所が次の選択肢となります。より柔軟な選択肢を提供するために、1982年の国連海洋法条約では、締約国が国際司法裁判所(ICJ)、国際海洋法裁判所(ITLOS)、附属書VIIに基づく仲裁機関、附属書VIIIに基づく仲裁機関の4つの司法機関のうち1つを選択することを宣言できると規定されている(14) 。特に、1945年以来国連と並んで設置されている裁判所であるICJを除き、残りの機関は1982年の国連海洋法条約の規定に基づいて新たに設立された。注目すべきことに、1982年の国連海洋法条約は自動デフォルトメカニズムを創設した。したがって、当事者が管轄を選択する声明を出さない場合、または異なる機関を選択した場合、付録 VII に基づいて設立された仲裁が紛争を解決するための必須の管轄機関となります。
このデフォルトメカニズム規定は、紛争解決機関を選択する際の柔軟性と、締約国が1982年の国連海洋法条約の解釈と実施に関する意見の相違について他の加盟国との紛争を解決するために附属書VIIに基づいて設立された仲裁を一方的に開始する権利を行使できる場合の効率性の両方を保証します。一方的に訴訟を起こす権利は、1982年の国連海洋法条約が包括的な条約であり、加盟国は条約を批准する際にいかなる規定にも留保を付けることができず、したがって、条約第15部に規定されている紛争解決メカニズムの強制的な権限に自発的に拘束されるという前提に基づいて規定されています。
しかし、紛争解決メカニズムにさらなる柔軟性を持たせるため、また、1958年の紛争解決議定書の厳格な規定の限界(多くの国が批准しなかった原因)を克服するために、1982年の国連海洋法条約では追加の例外と制限が規定されました。したがって、沿岸国の主権的権利及び管轄権の行使に関する条約の規定の解釈や適用に関する紛争は、当然、司法機関による強制的な紛争解決メカニズムの対象から除外される(15) 。国境画定、海上境界、船舶の軍事活動に関連する紛争、または国連安全保障理事会で審議中の紛争も、司法機関の強制的な紛争解決メカニズムから任意で除外されることがある(16) 。したがって、加盟国がこれら3つの種類の紛争を除外する宣言を行った場合、他の国は、条約の規定に基づいて、これらの紛争について司法機関に訴訟を提起することができなくなります。
一部の紛争は、デフォルトまたは選択により司法機関による強制的な紛争解決の対象から除外されるものの、加盟国は依然として、意見交換の義務を含め、他の平和的手段によって紛争を解決する義務を負っている。特に、1982年の国連海洋法条約では、除外された紛争については、当事者が紛争解決措置に関する勧告を行うために一方的に強制調停を要請できると規定されています。
1982年の国連海洋法条約は、柔軟かつ独創的な規定により、多層的な紛争解決メカニズムを構築し、紛争解決手段や機関に関して当事者に柔軟性と選択の自由を保障するとともに、当事者の紛争解決プロセスを促進する条件を整えていると言えます。特に、1982 年の UNCLOS の紛争解決メカニズムは、加盟国が国際司法機関に対して一方的に訴訟を起こす権利を規定した最初の先駆的なメカニズムです。この規制のおかげで、海上での国家間の多くの紛争が解決され、国家間の意見の相違も縮小されました。 1982年に国連海洋法条約が発効して以来、29件の海洋紛争が国際司法裁判所を通じて解決され、18件の紛争が国際海洋法条約(ITLOS)を通じて解決され、11件の紛争が附属書VIIに基づいて設立された仲裁を通じて解決されました。
持続可能な価値、未来へ
1982 年の UNCLOS は、包括的かつ普遍的な法的枠組み、革新的な紛争解決メカニズムを創設し、海上の平和と安定を促進するだけでなく、持続可能で未来志向の海洋ガバナンスの方向性に関連する進歩的な規定も備えています。協力義務は条約の中心であり、海洋環境の保護と保全の分野における協力、海洋科学調査における協力、科学技術の移転における協力、半閉鎖海域における協力、海上犯罪の撲滅における協力などに関する規定を含む、条約の 14 の異なる条項で 60 回言及されています...
海洋環境の保護と保全の分野では、1982 年の国連海洋法条約により、排他的経済水域内の沿岸国の一貫した規制と責任が規定されています。同時に、海域の範囲内での国家間の協力義務を規定しています。特に、1982 年の UNCLOS の第 12 部は、11 条で海洋環境の保護と保全を規制することに専念しています。
1982 年の UNCLOS の第 12 部には、国家に適用される一般的な義務を規定する第 1 項に加えて、地域および国際レベルでの協力、開発途上国への技術支援、海洋汚染源の影響の評価に関する具体的な規定が含まれています。 1982 年の UNCLOS では、国内および国際レベルで海洋汚染を防止するための規制を策定し、海洋汚染行為の責任を決定するために、陸地からの発生源、海域での開発活動からの発生源、船舶からの発生源、海洋への投棄および投棄からの発生源、空気および大気からの発生源の汚染原因を分類しています。さらに、1982 年の UNCLOS には、氷で覆われた海域に関する具体的な規定があり、環境保護の分野における他の専門的な国際条約との関係が定義されています。
海洋科学調査の分野において、1982 年の UNCLOS は、沿岸国の主権と管轄権と、コミュニティの利益との間の調和のとれた保証を強調しています。したがって、この条約では、各国および国際機関が海洋科学的調査から得られた情報と知識を普及させることを規定しています。同時に、条約は各国及び国際機関に対し、海洋科学研究から得られた科学的データや情報の交換、特に開発途上国への知識の移転に協力し、促進すること、また海洋科学研究の分野における開発途上国の能力構築を強化することを義務付けている(17) 。
特に、科学技術の重要性を認識し、同時にこの分野における国家間の不平等を克服するために、1982 年の UNCLOS では、第 14 部を技術移転の問題の規制に充てました。したがって、この条約は、各国が直接または国際機関を通じて協力し、公正かつ合理的な形態と条件の下で海洋科学技術の発展と移転を積極的に促進するという原則を定めています。条約は、海洋資源の探査、開発、保全、管理、海洋環境の保護、保全、海洋科学調査、および開発途上国の社会的、経済的進歩の促進に適した海洋環境におけるその他の活動について、開発途上国、内陸国および地理的に不利な立場にある国による技術支援の必要性を特に重視しています。条約はまた、持続可能な開発のための海洋資源の利用と保全を目的とした海洋科学研究を奨励し促進するために、国家および地域の海洋科学技術研究センターの設立を奨励しています。
将来の持続可能な開発のために貴重な海洋遺伝資源を保全するという目標を達成するために、条約加盟国は現在、国家管轄権外の地域における生物多様性に関する協定の交渉と署名のプロセスに参加している(18) 。同時に、科学技術の発展や、気候変動による悪影響、海面上昇、伝染病の影響など新たな課題の顕在化に伴い、加盟国は条約の規定を補完するための議論を継続していきます。
ベトナム - 1982年の国連海洋法条約の責任ある加盟国
ベトナムは国家統一直後から、第3回国連海洋法会議に積極的に参加しました。同時に、1977年5月12日に領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚に関する宣言を発布した(19) 。この宣言は1977年に発表されたが、その内容は1982年に各国が署名した国連海洋法条約の規定と完全に一致している。1994年、ベトナムは1982年の国連海洋法条約が正式に発効する1994年12月以前に、63番目に批准した国となった。1982年の国連海洋法条約批准を定めた国会決議は、ベトナムが1982年に国連海洋法条約を批准することにより、国際社会と協力して公正な法秩序を構築し、海上での発展と協力を促進する決意を表明したことを明確に確認した(20) 。
ベトナムは1982年にUNCLOSの正式加盟国となって以来、領土境界、海洋、漁業、石油・天然ガス、海洋・島嶼環境保護など多くの分野で同条約の規定を規定する国内法文書を多数発行してきました。特に、2012年にベトナムは、ほとんどの内容が1982年のUNCLOSと整合するベトナム海洋法を発行しました。
ベトナムは、1982年の国連海洋法条約に基づく義務を果たし、条約加盟から15年後の2009年に、北部地域の大陸棚延長境界を国連大陸棚限界委員会に提出した(21) 。さらに、ベトナムはマレーシアと協力して、両国が境界のない大陸棚が重なり合っている東シナ海南部の共通延長大陸棚の外側の境界線をCLCSに提出した(22) 。
ベトナムは平等、理解、相互尊重の精神、国際法、特に1982年の国連海洋法条約の尊重に基づき、多くの近隣諸国と重複する海域の境界を定めることに成功しました。ベトナムと中国は、海洋境界線の設定とともに、トンキン湾での漁業協力についても合意に達し、共同漁業協力水域の設定や、海上での犯罪や違反行為を防止するための共同パトロールの設置を行った(23) 。
これまで、ベトナムと近隣諸国間の海洋境界画定協定は、国際紛争の平和的解決の原則、特に1982年の国連海洋法条約に基づく国際法に基づいて実施されており、ベトナムと近隣諸国間の平和的、安定的、発展的な関係の促進に貢献しています。ベトナムは海洋境界線の設定に加え、両国間の境界未画定海域における歴史的水域についてもカンボジアと合意に達した。同時に、マレーシアとともに、両国間で境界が定められていない大陸棚の重複領域に共同の石油・ガス採掘区域を確立する。
ベトナムは、カンボジアとの重複地域、ベトナム、マレーシア、タイの三国間の重複地域、ベトナムとブルネイ、ベトナムとフィリピン間の重複の可能性がある地域など、近隣諸国との間で依然として境界が定められていない海域において、沿岸国の排他的経済水域や大陸棚に対する主権と管轄権を常に尊重しつつ、根本的かつ長期的な解決策を見出すための交渉を推進している。 (24)ベトナムは、現状維持、事態をさらに複雑にする行動の不採用、武力の行使や武力の威嚇を行わないことを基本とした安定の維持を支持する。
特にホアンサ島とチュオンサ島の2つの島については、一方ではベトナムは、これら2つの島に対するベトナムの主権を証明する十分な歴史的、法的証拠を有していると主張している。一方、ベトナムは、ホアンサ諸島とチュオンサ諸島をめぐる紛争の解決の問題と、1982年の国連海洋法条約の原則と基準に基づくベトナムの主権、主権的権利、管轄権の下にある海域と大陸棚の保護の問題を区別する必要があると判断した。これに基づき、ベトナムは東海における関係国の行動宣言(DOC)に署名し、実施しており、中国および東南アジア諸国連合(ASEAN)加盟国と東海における行動規範(COC)について積極的に交渉している。

2018年10月22日、第8回中央会議第12セッション「2030年までのベトナム海洋経済の持続可能な発展戦略、2045年までのビジョン」の決議が発表されました。この戦略では、「海は祖国の神聖な主権の構成要素であり、生活空間であり、国際交流の玄関口であり、祖国の建設と防衛の大義と密接に関連している」と明確に定義されています(25) 。この戦略は、ブルーマリン経済の発展、生物多様性の保全、歴史的伝統と海洋文化の保護と促進、先進的かつ現代的な科学技術の獲得、質の高い人材の活用といった目標に加え、ベトナムが海洋に関する国際的および地域的な問題の解決に積極的かつ責任を持って参加するという2045年に向けたビジョンを定義しています。
この精神に基づき、ベトナムと他の11か国は2021年にUNCLOS1982友好国グループを設立し、各国が海洋に関する問題を議論するためのオープンで友好的なフォーラムを創設し、UNCLOSの完全な実施に貢献することを目指しています(26) 。現在、ベトナムは、国家管轄権外の海域における生物多様性の保全、気候変動による海への悪影響への対応、新型コロナウイルス感染症のパンデミック、人身売買、不法移民など新たな非伝統的な安全保障上の課題を背景とした海上活動の管理など、海洋の新たな問題について議論する多国間フォーラムに積極的かつ積極的に参加しており、今後も参加を続ける予定である。
「海洋の憲法」とも呼ばれる国連海洋法条約(UNCLOS)は、40年前に署名され、国際法の発展における歴史的な節目となり、平和で安定した海洋統治のための包括的な法的枠組みを構築し、国家間の協力と海洋の持続可能な開発を促進しました。現在世界で最も多くの加盟国を擁する多国間組織である国連は、1982年の国連海洋法条約の役割を繰り返し認め、海上および海洋におけるあらゆる活動において同条約を遵守する必要性を強調してきた(27) 。 ASEANは、ハイレベル声明において、地域の平和と安定を維持し、海洋紛争を平和的に管理・解決するために、1982年の国連海洋法条約を実施することの普遍的な価値と重要性を常に強調してきた。沿岸国として、積極的かつ責任あるメンバーとして、ベトナムは、1982年の国連海洋法条約が国家の海洋経済の管理と発展に重要な役割を果たす国際法の条項の一つであることを常に主張しています。同時に、これはベトナムが近隣諸国との海洋紛争を平和的に解決し、東海の平和的かつ持続可能な管理を実現するための基礎となる。
----------------------------
(1)ガブリエーレ・ゲッチェ=ワンリ「国連海洋法条約:実践的な多国間外交」第3巻、1998年。 LI、国連、 2014 年 12 月、 https://www.un.org/en/chronicle/article/united-nations-convention-law-sea-multilateral-diplomacy-work
(2)参照:1982年にUNCLOSに署名・批准した国のリスト、 https://www.un.org/depts/los/reference_files/UNCLOS%20Status%20table_ENG.pdf
(3)海洋法に関する4つの条約と1958年の議定書の全文、 https://legal.un.org/avl/ha/gclos/gclos.html
(4)大陸棚条約第2条は、各国が自国の資源開発能力に応じてその限度まで大陸棚を決定できると規定している。この基準は、科学技術の発展レベルと先進国の強さに完全に依存します。
(5)紛争解決議定書は18カ国のみが批准している。議定書は、ICJに強制管轄権を与えることに加えて、各国が相互合意に達した場合には他の裁判所や法廷の管轄権も認めている。しかし、最終的な目標は、海洋紛争を解決するための司法機関の強制管轄権を確立することである。参照:「批准国一覧」 https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=08000002800332b0
(6)1982年のUNCLOSの規定以前は、1952年のサンティアゴ宣言において、チリ、エクアドル、ペルーを含むラテンアメリカの3か国が最初に200海里の漁業水域を主張し、この水域は浅く温暖な海域であり、魚種の成長と発達に適していると主張した。参照: SN ナンダン:「排他的経済水域: 歴史的視点」、 https://www.fao.org/3/s5280T/s5280t0p.htm
(7)延長大陸棚の幅は、自然大陸棚の幅と等しいか、基線から350海里、または2,500メートル等深線から100海里に等しいものとすることができる。大陸棚の法的幅を決定する方法の詳細は、1982 年の国連海洋法条約第 76 条に規定されています。
(8)大陸棚限界委員会(CLCS)は、200海里を超える大陸棚の限界に関する各国の意見を審議するために1982年に国連海洋法条約に基づいて設立された3つの機関のうちの1つである。委員会は 5 つの地理的地域を代表する 21 名のメンバーで構成されています。
(9)条約は、第10部に第124条から第132条までの9つの規定を留保する。排他的経済水域に関する条約(第69条、第70条)と海洋科学的調査に関する第254条の2つの規定は、地理的に不利な国と内陸国の権利を規制するものである。
(10)群島国は、一つの群島のみから構成されているものの、地理的には異なる島々によって隔てられているという特殊性を有するため、第4部第46条から第54条までに規定する特別制度を適用する権利を有する。したがって、群島国は、群島の最外縁の島々の最外縁点と低潮高を結んだ群島基線の方法を適用することができる。ただし、これらの基線の線が主要な島々を囲み、水域の面積とサンゴ礁を含む陸地の面積の比率が 1:1 から 9:1 の間となる領域を確立することを条件とする。さらに、群島国は、その群島水域(群島基線によって囲まれた水域)に特別な法的地位を適用する権利を有します。
(11)海底機構は、第11部に詳述する海底機構の組織構造、機能及び任務に関する規則並びに1982年の国連海洋法条約第11部の実施に関する協定に基づき、人類共通の遺産として海底資源を管理することを目的として海底で行われる活動を組織し、統制する機能を有する組織である。
(13)国連憲章第33条
(13)意見交換の義務は、1982年の国連海洋法条約第283条に規定されている。相当の期間は、個々の具体的な事案の状況に応じて決定されます。
(14)1982年の国連海洋法条約第287条に規定されている。附属書VIIに基づいて設立される仲裁と附属書VIIIに基づいて設立される仲裁は、いずれも特別仲裁である。付属書 VII に基づいて設立された仲裁裁判所は、1982 年の UNCLOS の解釈と適用に関連するあらゆる種類の紛争について一般的な管轄権を持ちますが、付属書 VIII に基づいて設立された仲裁裁判所は、海洋科学調査に関連する紛争についてのみ管轄権を持ちます。
(15)、(16)1982年国連海洋法条約第297条の規定
(17)1982年国連海洋法条約第244条
(18)これまでに、交渉プロセスは5回の政府間総会で開催されてきた。参照: https://www.un.org/bbnj/
(19)宣言の全文は、国連海洋法データベースで閲覧可能。https ://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/VNM_1977_Statement.pdf
(20)1994年6月23日の1982年国連海洋法条約の批准に関するベトナム社会主義共和国国会決議第2項
(21)ベトナムは2009年5月7日に大陸棚延長地域に関する意見書をCLCSに提出した。https ://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_vnm_37_2009.htm
(22)ベトナムとマレーシアが2009年5月6日に提出した大陸棚延長の限界に関する共同提案、 https://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_mysvnm_33_2009.htm
(23)ベトナム社会主義共和国政府と中華人民共和国政府間のトンキン湾漁業協力協定、2000年、 http://biengioilanhtho.gov.vn/medias/public/Archives/head/Cac%20nuoc%20bien%20gioi/UBBG.Viettrung09.pdf
(24)ベトナムが北部地域における大陸棚延長の主張を提出した後、フィリピンはベトナムの大陸棚がフィリピンの大陸棚と重なる可能性があることを懸念する口上書を送った。しかし、現在まで重複領域は具体的に特定されていません。同様に、ベトナムの大陸棚延長によってブルネイとの重複領域も生まれる可能性がある。
(25)第12期中央執行委員会第8回会議文書、中央党事務所、ハノイ、2018年、115ページ。 81
(26)UNCLOSフレンズグループは、ベトナムが主導し、設立キャンペーンの共同議長を務め(ドイツと共同)、中核グループ(アルゼンチン、カナダ、デンマーク、ドイツ、ジャマイカ、ケニア、オランダ、ニュージーランド、オマーン、セネガル、南アフリカ、ベトナムの12か国を含む)に参加した最初のグループである。現在までに、UNCLOS 友好国グループにはあらゆる地理的地域を代表する 115 か国が参加しています。
(27)参照:第76回国連総会議長アブドラ・シャヒド声明、国連、2022年4月29日、 https://www.un.org/pga/76/2022/04/29/40th-anniversary-of-the-adoption-of-the-united-nations-convention-on-the-law-of-the-sea-unclos/
出典: https://tapchicongsan.org.vn/web/guest/quoc-phong-an-ninh-oi-ngoai1/-/2018/826103/cong-oc-cua-lien-hop-quoc-ve-luat-bien-nam-1982--bon-muoi-nam-vi-hoa-binh%2C-phat-trien-ben-vung-bien-va-dai-duong.aspx


![[写真] ファム・ミン・チン首相がプロジェクトの困難を取り除く会議を主宰](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/3/30/7d354a396d4e4699adc2ccc0d44fbd4f)














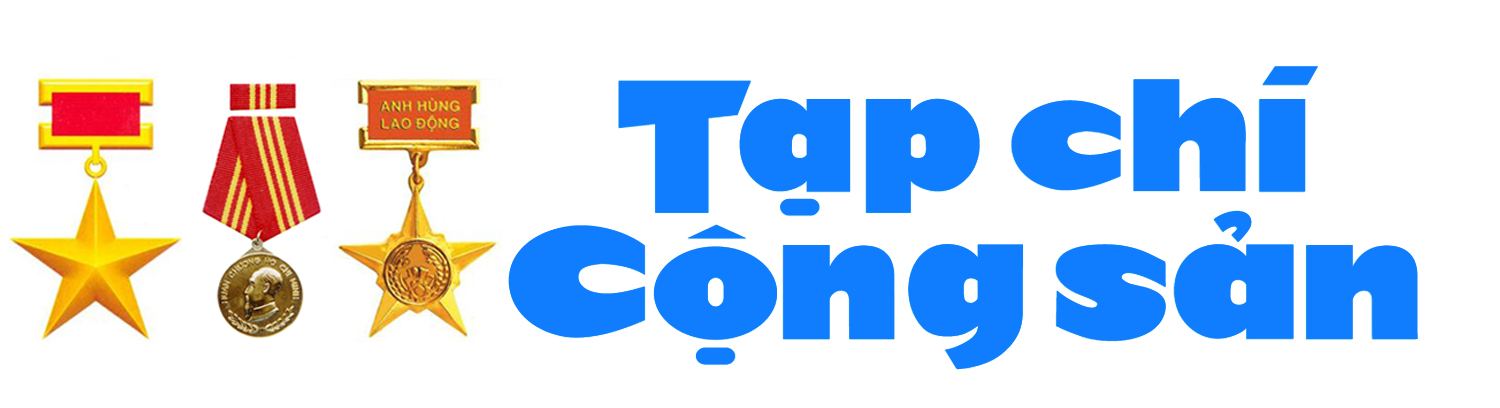

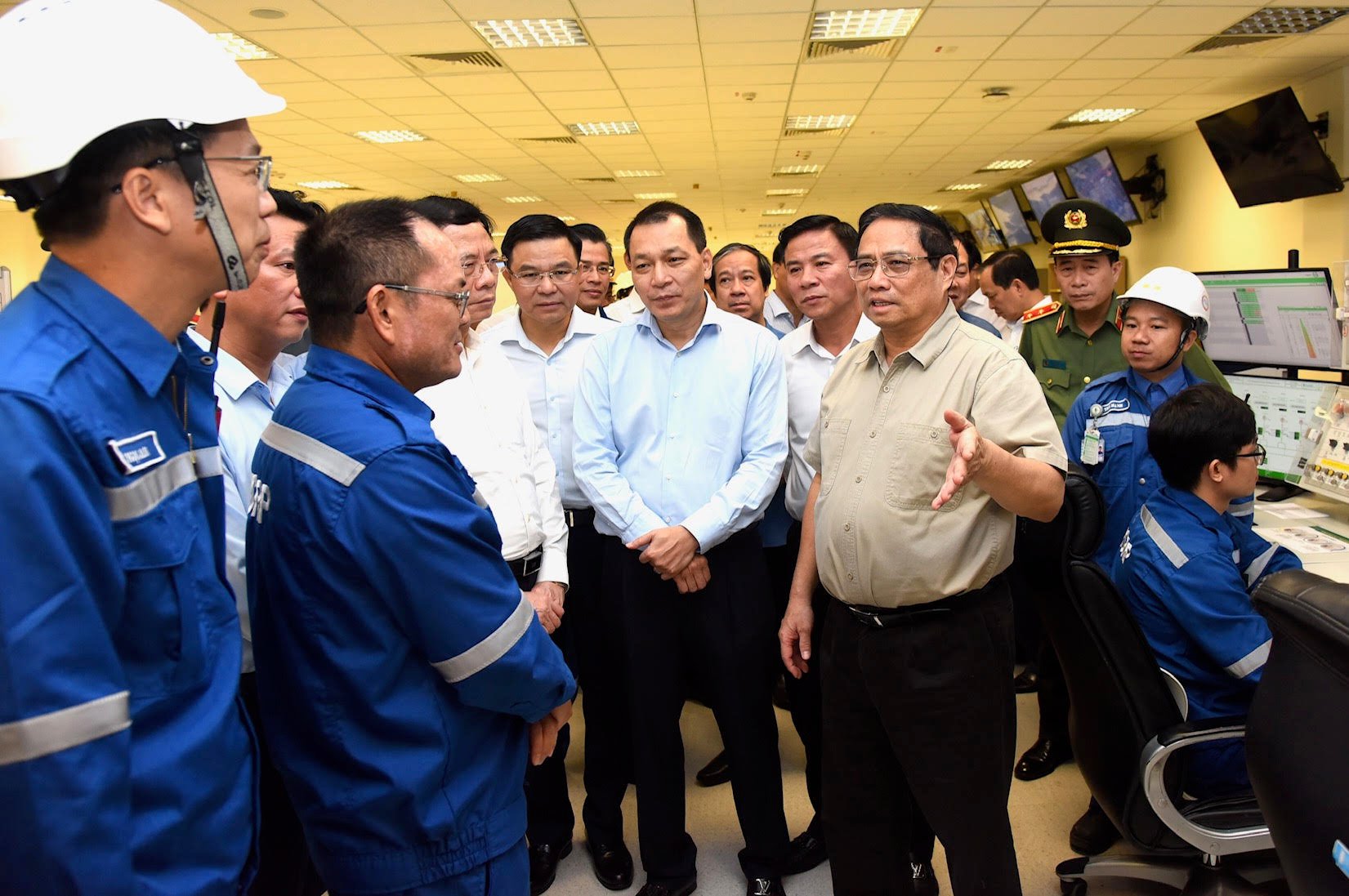






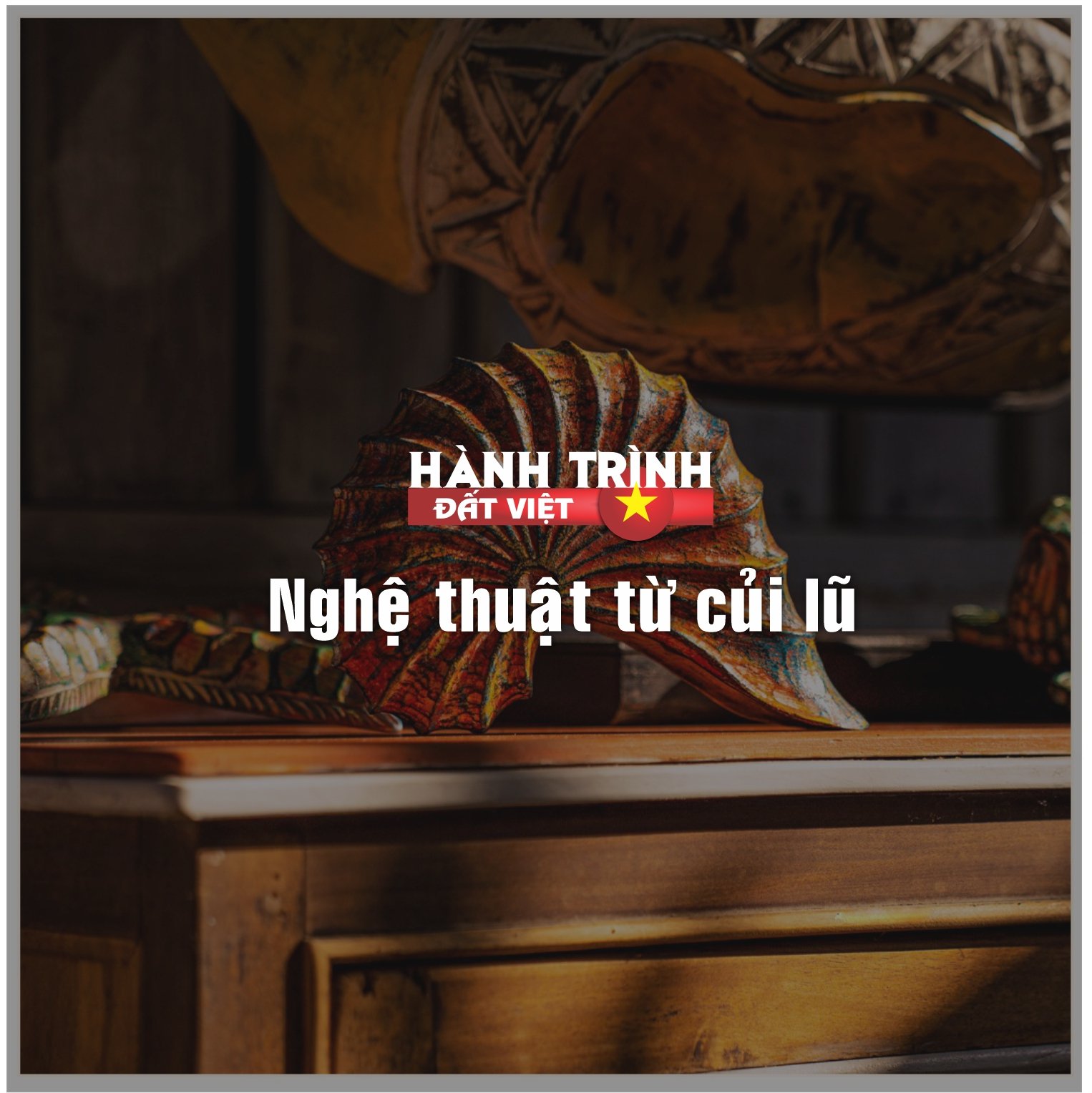





































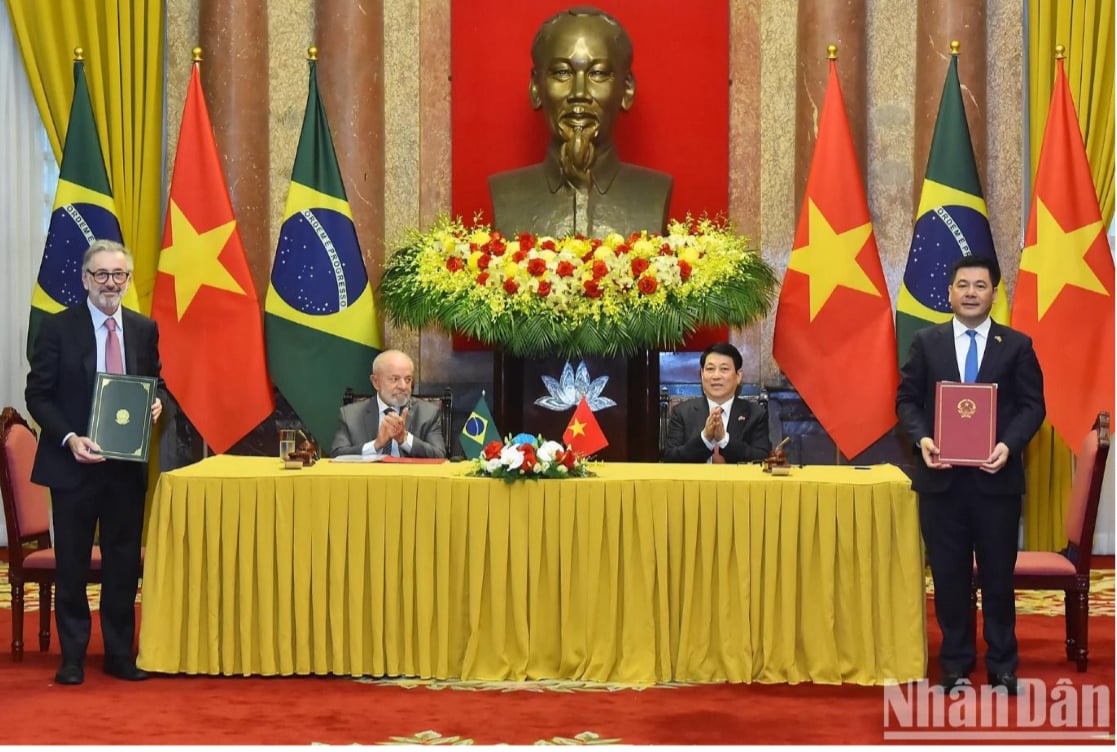

















![[レビュー OCOP] アン・ラン・フオン ベット・イェン・キャット](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/3/27/c25032328e9a47be9991d5be7c0cad8c)







コメント (0)