食欲は単に食べたいという欲求以上のものです。むしろ、 The Conversation (オーストラリア)によると、それは感情、行動、認知、生理学の身体プロセスの複雑な組み合わせです。
私たちが病気のとき、炭水化物を渇望するように刺激する生物学的メカニズムは、次のような目的を果たします。
免疫力を高める

病気のときの体の変化により、炭水化物を多く含む食べ物が欲しくなることがあります。
病気が体を攻撃すると、免疫システムが活性化され、病原体を排除します。したがって、免疫システムが正常に機能するには、追加のエネルギーが必要です。この現象は多くの場合、体の代謝の増加につながり、エネルギーの必要量と栄養素の吸収を押し上げます。
糖分やデンプンを含む食品は、素早く豊富なエネルギー源となります。しかし、必要量を超えて糖分を摂りすぎると、体内で炎症が起こりやすくなり、回復の妨げになります。
ストレス反応による
病気になると身体にストレスがかかります。ストレスにより、アドレナリンとコルチゾールというホルモンが増加し、ストレスの多い状況に対処するために体内のエネルギーが動員されます。
したがって、ストレスが長引くと、体のエネルギーバランスが崩れ、栄養不足や食欲の刺激を引き起こします。その結果、体はデンプンや砂糖などエネルギーの高い食べ物を欲するようになります。
脳の報酬システム

患者が食欲を示さない場合、特に炭水化物を多く含む食べ物を好まない場合、疲労、不快感、吐き気、または味覚の変化が原因である可能性があります。
糖分やデンプンを多く含む食品を食べると、脳の報酬系が簡単に活性化され、ドーパミンやセロトニンなどの快感神経伝達物質の分泌が増加します。
しかし、病気の人全員が炭水化物を欲しがるわけではありません。患者が食欲を示さない場合、特に炭水化物を多く含む食べ物を好まない場合、疲労、不快感、吐き気、または味覚の変化が原因である可能性があります。
その他の原因としては、代謝が遅いことや、お粥、スープ、水、お茶などの液体食品を過剰に摂取することが挙げられます。 The Conversation によると、これらの食品を食べると満腹感が増し、食欲が減退するそうです。
[広告2]
ソースリンク


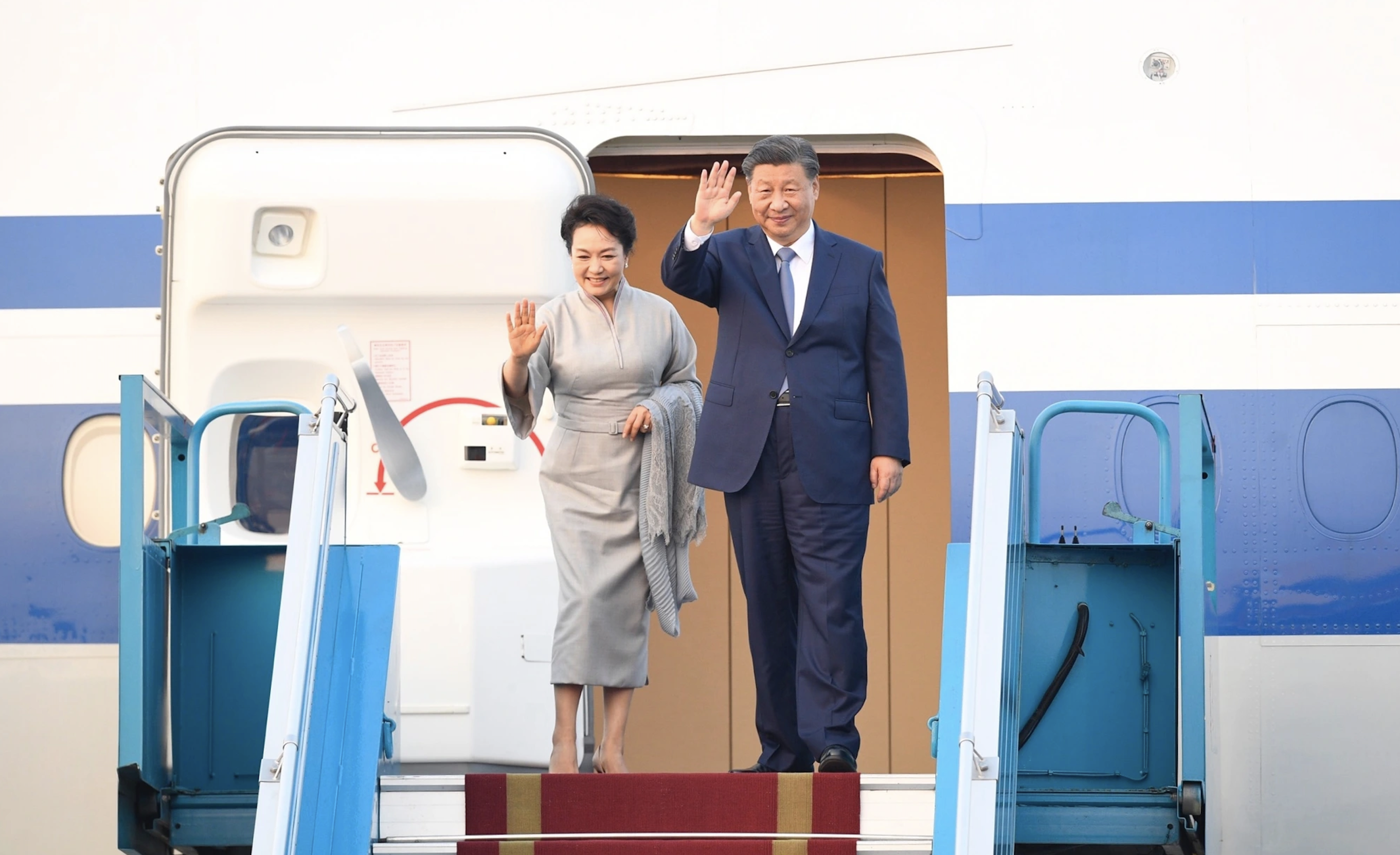




![[写真] ファム・ミン・チン首相が4月の政府立法特別会議の議長を務める](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/13/8b2071d47adc4c22ac3a9534d12ddc17)








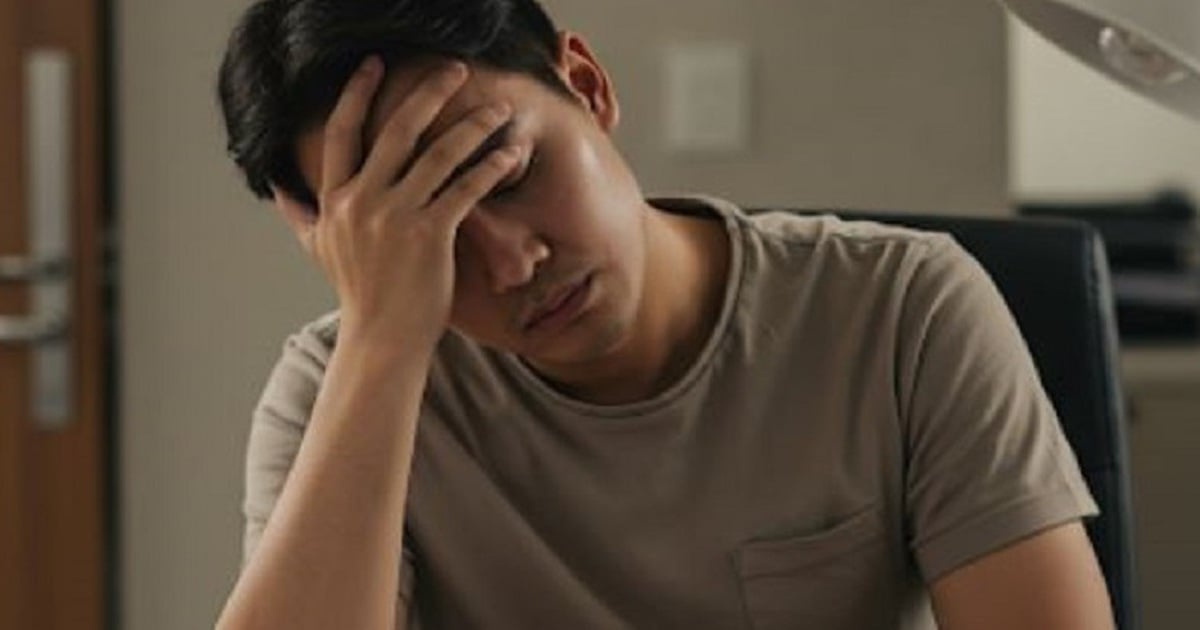


















































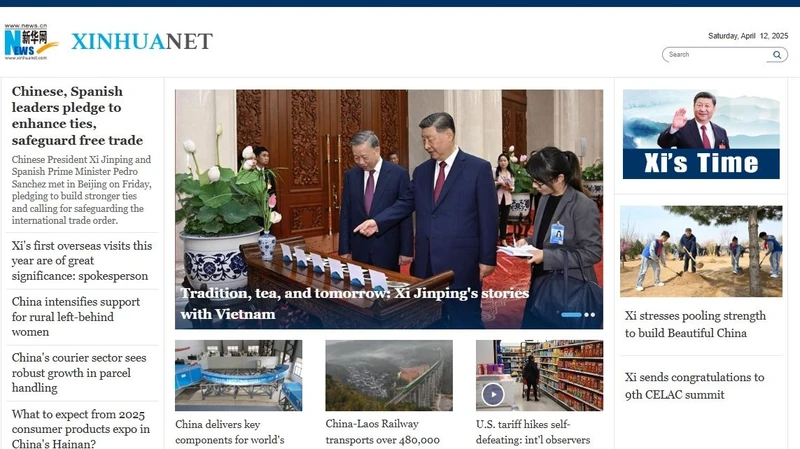
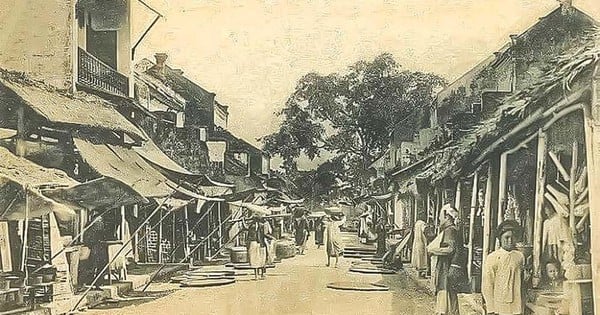


























コメント (0)