スミスは生涯をかけて著した『国富論』の中で、国家の繁栄につながる要因を体系的に分析して指摘した。アダム・スミスの思想は、当時、経済と政治の基盤の欠陥を照らす明るい松明のようでした。彼の作品はヨーロッパで好評を博しただけでなく、アメリカの建国の父たちによっても熱心に読まれました。
しかし、アダム・スミスの思想は政治経済の領域にとどまらず、彼は道徳哲学者でもありました。彼が 1759 年に出版し、死の数か月前に第 6 版の編集を続けた最初の本は、 『道徳感情論』です。したがって、アダム・スミスの包括的な思想を理解するには、彼の政治経済学に統合された倫理の教義を無視することは不可能です。

アダム・スミスは国家の繁栄につながる要因を指摘した。
スミスは、第一次産業革命が起こり始め、実験と理性に基づいた知識の構築に重点を置いたヨーロッパ啓蒙主義が最高潮に達していた時代に生きていました。スミスの最も重要な教師(フランシス・ハチソン)と最も親しい知的友人(デイヴィッド・ヒューム)は、ともに影響力のある啓蒙思想の哲学者であった。このような文脈において、スミスの全体的な思想は、社会における人々の関係(経済的・政治的・道徳的)で何が起こるかについての彼の経験的観察に基づいています。
スミスは良い社会を望んでいた。そして彼は、その目標に至った要因を特定しようとしました。スミスは「その構成員の大多数が貧しく惨めな状態では、社会は繁栄し幸福にはなれない」と書いている[1]。彼は、経済がどのように発展すれば人口の大多数の貧困を削減できるかを懸念していた。しかし、社会で生きる人間には精神的な欲求もあるため、お金で幸福は買えないと彼は信じています。 [2]
アダム・スミスの思想が時代を超えて生き残ったのは、彼が極端に陥らず、あらゆる状況で思想を展開しなかったからだ。彼にとって、経済、政治、社会生活は切り離せない要素です。したがって、市場経済、国家の役割、社会関係に関する彼の理論は、今日の世界においても依然として意味を持ちます。
生産性の向上は国家の繁栄の基盤です。
英国が産業革命の真っ只中に執筆活動を行っていたため、スミスは国家の繁栄につながる根本的な要因を指摘する実証的な観察を行う機会を得た。スミスにとって、国家の富とは支配層の富の増加ではなく、大多数の人々の物質的な生活の向上であった。ここでは経済成長(商品やサービスの生産量の増加)が生活を向上させる鍵となります。
スミスは経済成長は経済の生産性向上能力に依存すると分析し指摘した。そして生産性は分業に依存します。分業が進むほど専門性が高まり、創造性と新技術が増し、生産性が向上します。
しかし、分業の程度は市場の規模によって決まります。スミスは次のように書いている。「交換力は労働の共有につながるため、この共有の範囲は常にその力の規模、言い換えれば市場の規模によって制限される。市場が非常に小さい場合、誰も自分の消費量を超える労働の余剰を、自分が必要とする他人の労働と交換する可能性がないため、一つの職業に全時間を費やす動機を持たない。」[3]
したがって、市場規模の鍵となるのは「交換力」であり、人々が売買する自由度が高ければ高いほど、市場は大きくなることを意味します。世界規模で見ると、貿易が自由化すればするほど市場が拡大し、分業、専門化、生産性の向上が促進されます。つまり、経済的自由は物質的な生活を向上させるための基盤なのです。そして現実はスミスの発言を証明した。今日、貿易と生産性のつながりは明らかです。貿易の増加は生産性を向上させる上で重要な要素である。[4]過去数十年間のグローバル化の進展により、世界中の何十億もの人々が極度の貧困から脱出しました。世界貿易機関(WTO)と世界銀行(WB)は、「貿易は(これまで)貧困削減に重要な貢献をしてきたが、開発途上国が国際市場へのさらなる統合を図ることは、貧困を終わらせ、誰一人取り残さないために不可欠となるだろう」と指摘している[5]。
開発モデル
スミスは経済的自由を、人間の本性と一致する「自然的自由のシステム」とみなし、平等な競争の場を確保するために制限された国家によって規制された社会において、個人の創造的潜在能力を解き放つことができるものとした。
スミスは、「国家を低位で原始的な状態から富の頂点へと引き上げるには、平和、軽い税制、そして許容できる司法制度以外にはほとんど何も必要ありません。他のすべては自然の成り行きに従って進むのです」と主張した。
スミスにとって、自然法則は自由市場における個人間の相互作用から形成され、社会全体にとっての共通善につながります。国家の政策はさまざまな主観的および客観的な理由により間違いを犯すことが多いため、自由市場への国家の介入はこのルールを覆すことになります。
スミスは次のように書いている。「制度の信奉者は、しばしば自らを非常に賢い人間だと思い込み、国家の理想的な計画という想像上の美しさにあまりにも夢中になりすぎて、そのいかなる部分においても、そこから少しでも逸脱することを許さない。…彼は、チェス盤の上で手が駒を配置するように、大社会の様々な構成員を配置できると想像しているようだ。…人間社会という巨大なチェス盤上では、それぞれの駒が独自の運動原理を持っており、それは国家が押し付けようとする原理とは全く異なることを、彼は考慮していない。」[6] この発言は、国家を経験したことのない者から発せられたものではない。興味深いことに、スミス自身も1790年に亡くなるまで10年以上にわたり国家公務員(スコットランド税関職員)を務めていました。[7]
より具体的に言えば、スミス氏の上記の発言は 3 つの密接に関連した点に基づいています。まず、限られた資源で自分の生活を向上させる最善の方法を常に模索するのは、すべての個人の自然な傾向です。第二に、最善の選択(決定)を下すには、能力とリソースの面で自分自身を最もよく知っているのは(国家ではなく)個人だけである。第三に、正義が守られた社会において、個人が自由に自らの利益を追求できるとき、それは社会全体にとって良い結果につながる。なぜなら成功するためには、個人が最善を尽くし、自発的に協力し合わなければならないからだ。[8]これはスミスの言うところの「見えざる手」の働きである。
しかしスミスは、市場を支援し、良い社会を築く上での国家の役割についても注意深く指摘した。平和と安全を維持するのは国家の機能です。経済発展を支援する公共サービス(交通インフラなど)を提供することも、国家の重要な役割です。政府がその責務を効果的に遂行すれば、税金は適切に使用され、国民の頭上に「降りかかる」ことはありません。スミスは、単純で透明性があり、各人の収入に比例した税制を提唱した。
そして、効果的に機能し、社会全体にとって良い結果を生み出す自由市場は、国家によって保護された正義の基盤に基づいていなければなりません。スミスにとって、正義は国家が(1)生命、(2)財産、(3)国民の契約を保護するための明確な法律を持っているときに守られる。スミスは、国家が正義の名の下に市場や社会全体に過度に介入することがないように、正義の定義を注意深く制限した。[9]
スミス氏は、強力な企業が政府当局者と共謀し(縁故資本主義)、補助金などの政策を通じて利益を得たり、競争を制限する可能性が常に存在すると指摘した。彼は、この世からのいかなる提案も慎重に検討し、その意図を疑問視すべきだとアドバイスした。レントシーキングは不公平であるだけでなく(公共を犠牲にして少数の集団に利益をもたらすため)、経済成長を妨げます(資源配分を歪めるため)。[10]
「自然的自由システム」では、個人は競争や正義の執行だけでなく、繁栄し幸福な社会に不可欠な道徳的行為によっても規制されます。スミスはこう書いています。「幸福は平和と喜びの中にあります。平和のないところに喜びはありません。そして完全な平和があるところには、人を幸福にできないものはほとんどありません。」スミスは、平和を保つためには、正義、慎重さ、そして他人に利益をもたらす方法を知るという3つの基本的な道徳的価値観を持って生きることが必要だと指摘しました。そうして初めて各個人は真に幸福となり、社会は真に良いものとなるのです。[11]
上記3つの価値観が社会に広まることで、信頼関係の構築にもつながり、協働を促進し、より良い社会へと導きます。ここでの信頼とは、個人や国家機関が共通の期待に沿って確実に行動するという確信を意味します。個人レベルでは、個人がお互いを信頼すると経済取引が促進され、増加します。そして、国家が正義を守るために法律を透明かつ効果的に執行すると、国家の積極的な役割に対する人々の信頼が高まり、政策が成功するための条件が整えられます。
学者のフランシス・フクヤマ氏は、実証的研究を通じて、「国家の繁栄と競争力は、社会に存在する信頼のレベルという、単一の広範囲にわたる文化的特徴によって決まる」ことを明らかにした。信頼度の高い社会では「取引コスト」が削減され、経済活動が活発化して成長が促進されます。[12]
アダム・スミスの「自然的自由の体系」全体にわたって、人間の動機が貫かれています。生計を立てるために個人的な利益を追求することも動機の一つであり、信頼を得るために道徳的に行動することも動機の一つです。個人が公正な「ゲームのルール」を持つ自由市場で自由に交流できる場合、個人のインセンティブは社会の利益と一致することになります。
経済的自由は世界中の何十億もの人々の生活を改善しました。しかし、経済的自由は自然に得られるものではありません。それは社会(国家)の意図的な選択です。自由を尊重する社会では、アダム・スミスの「自然的自由のシステム」は、個々の人間に由来するその肯定的な特徴をすべて発揮する機会を持つでしょう。社会的な動物として、自由な人間は生き残り、繁栄するために、社会がどのように変化しても協力しようとします。自由な社会とは、時代のニーズに合わせて常に進化する、柔軟で創造的な社会です。
[1] アダム・スミス『国富論』 (シカゴ大学出版局、1976年)。
[2] デニス・ラスムッセン、「アダム・スミスによる不平等の問題」アトランティック誌、2016年6月9日。
[3] スミス『国富論』
[4] ゲイリー・ハフバウアーとジーザオ・ルー「貿易の増加:生産性向上の鍵」ピーターソン国際経済研究所、2016年10月。
[5] 「貿易と貧困削減:開発途上国への影響に関する新たな証拠」世界銀行グループと世界貿易機関、2018年12月11日。
[6] アダム・スミス『道徳感情論』 (オーバーランドパーク:Digireads.com Publishing、2018年)。
[7] ゲイリー・アンダーソン、ウィリアム・シュガート、ロバート・トリソン「税関のアダム・スミス」 『政治経済ジャーナル』 93巻2号、1995年、115~199頁。 4 (1985):740-759頁。
[8] ジェームズ・オッターソン『エッセンシャル・アダム・スミス』 (フレイザー研究所、2018年)。
[9] ジェームズ・オッターソン『エッセンシャル・アダム・スミス』 (フレイザー研究所、2018年)。
[10] ローレン・ブルベーカー「システムは不正に操作されているか?アダム・スミスによる縁故資本主義、その原因と解決策」ヘリテージ財団、2018年3月31日。
[11] マイケル・ブッシュ、「アダム・スミスと消費主義の幸福における役割:現代社会の再
「検討」『経済学主要テーマ』 10(2008):65-77。
経済学の主要テーマ、10、65-77。
[12] フランシス・フクヤマ『信頼:社会的美徳と繁栄の創造』 (ニューヨーク:フリープレスペーパーバック、1996年)。
(トラン・レ・アン - ジョアン・ワイラー・アーノウ 49歳 ラセル大学経済学・経営学教授)
[広告2]
ソースリンク





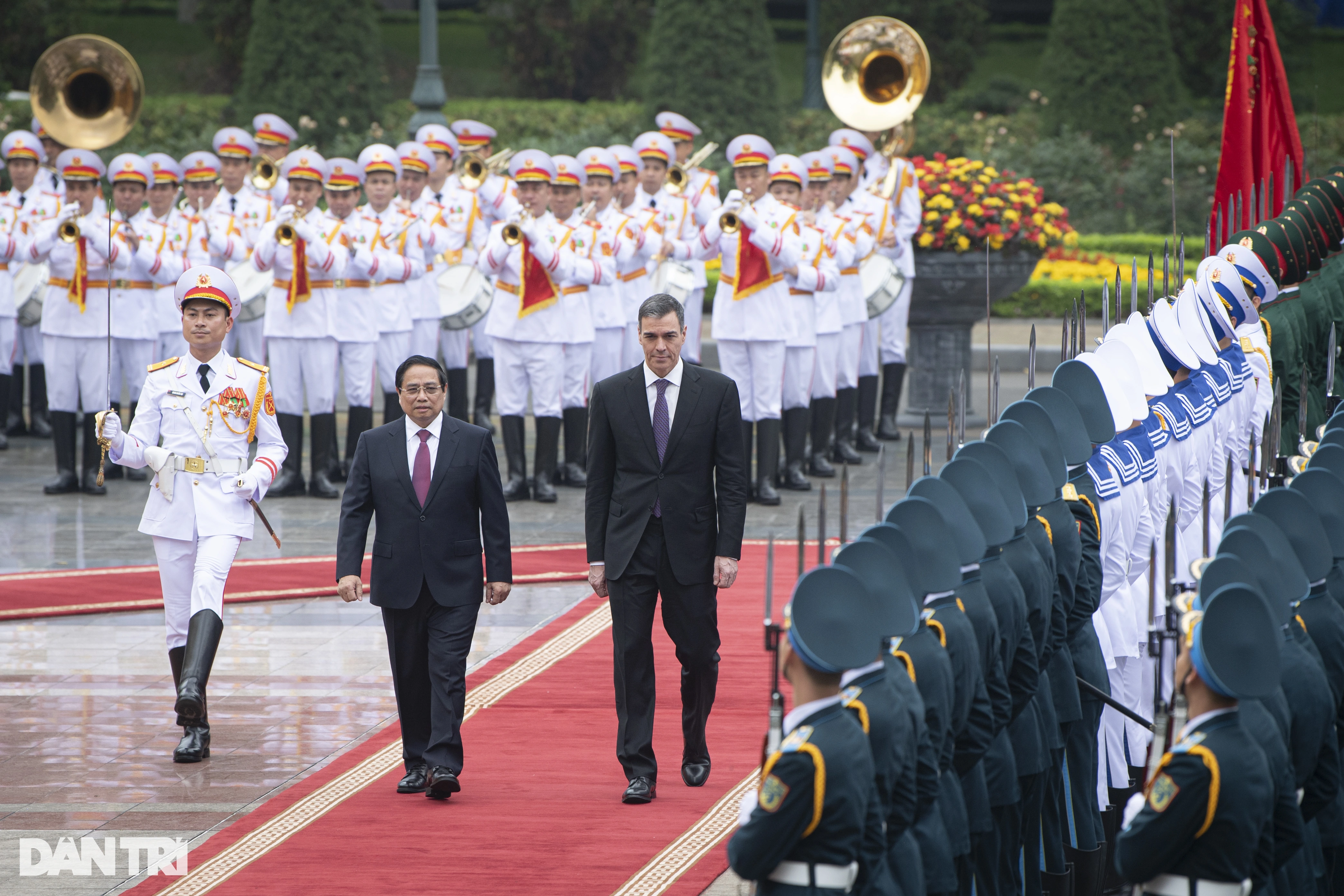
![[写真] クチトンネル訪問 - 英雄的な地下の偉業](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/8/06cb489403514b878768dd7262daba0b)










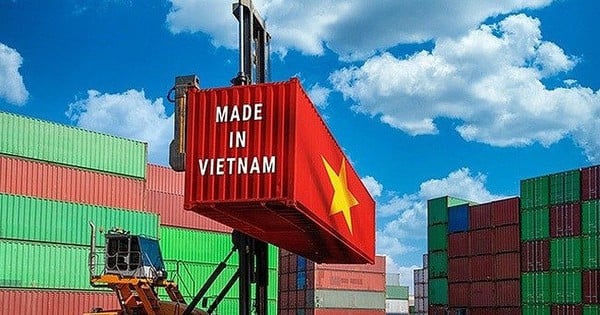



































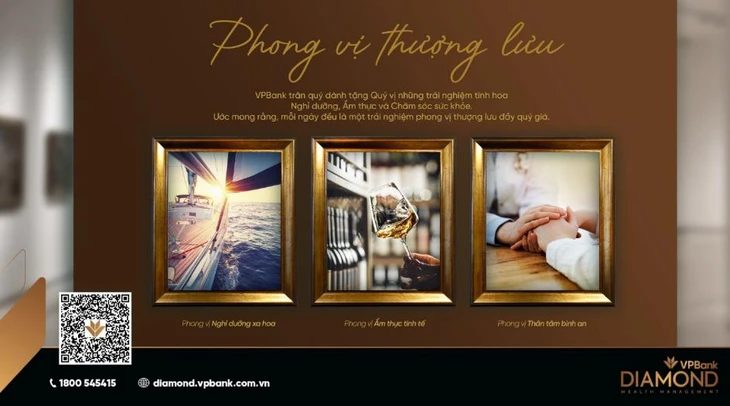



































コメント (0)