ユニークな工芸村
「省内に約200ある工芸村の中で、ここだけが紙作りをしているという点だけがユニークなわけではありません。機械を一切使わず、すべての工程が手作業で行われているという点もユニークです」と、グエン・ヴァン・ハ氏(ヴィン市ギフォン村フォンフー村、現第3集落)は誇らしげに語った。

ヴオン・ティ・ロアンさんは、2時間以上天日干しした紙を集めています。
グエン・ヴァン・ハ氏(64歳)とヴオン・ティ・ロアン夫人(58歳)は、先祖から受け継いだ職業を今も守り続けている数少ない家庭の一つです。ハさんはこう語った。「私が生まれたとき、杵で棍(とう)とニェットの樹皮(紙の原料)を杵で搗く音を聞きました。大人になって両親に、村の棍(とう)紙作りはいつ始まったのかと尋ねましたが、両親は首を横に振り、曽祖父の代からすでに存在していたと答えました。」
ハ氏によれば、昔の紙の主な材料はドウとニエットの木だったという。しかし、ドーの木は徐々に姿を消しました。村人たちは、クイホップ、クイチャウ、クエフォン、トゥオンズオンなどの山岳地帯の森の奥深くまで行ってそれを手に入れなければなりませんが、その量は多くありません。そのため、この材料が紙の製造に使用されることはほとんどありません。
一方、ニエットの木は、ギロク、クアロー、クアホイ(ゲアン)の砂浜に多く生えています。紙を作るには、外に出て枝を切るだけでいいのです。現在、都市部の発展に伴い、ゲアン省のニエットの木は存在しなくなったため、村人たちはタックハーとカムスエン(ハティン)の中州まで出向き、ニエットの木を探し出して持ち帰っています。
機械は紙を作ることができない
一枚の胴紙を作る工程や手順も非常に緻密で慎重です。家に持ち帰った後、ニエットの木の枝は剥がされ、樹皮だけが取られます。次に、作業員はナイフを使って殻の外側の黒い層を削り取り、紙のように薄くなるまで剥がします。

ギフォンの紙製品は、焼き魚を包んだり、扇子や書道用紙、提灯などを作ったりするのに使えますか。
その後、樹皮に石灰水(揚げた石灰)を詰めて鍋に入れ、1日以上煮続け、硬い樹皮を柔らかくします。次に、樹皮を剥ぎ、水に浸して石灰層を取り除き、石のまな板の上に置いて乳棒で叩きます。
次に、作業員は植物の残渣を取り、それを冷水で叩き、アサガオの植物から採取した粘液と混ぜます。最後に、混合物を紙枠の上に広げて乾燥させます。晴れていれば2時間ほどかかりますが、曇りであればさらに時間がかかります。
「土紙作りの特徴は、機械を一切使わず、完全に手作業で行われることです。杵の代わりにすりこぎ機を使うことも試しました。しかし、型に入れて乾燥させた後、紙にはなりませんでした。そのため、職人は土紙を一枚作るために、一日中ほとんど休みません」とハ氏は語った。
仕事を続けられないのではないかと心配している
村の職業の将来について尋ねられると、グエン・ヴァン・ハ氏は声を落とし、悲しそうな表情になった。彼はこう言った。「私たちの世代にとって、紙を作る仕事は飢餓救済の仕事とよく呼ばれていました。当時は経済が厳しく、人々の生活は多くの面で困窮していました。」

グエン・ヴァン・ハさんはイラクサの木の樹皮を削って紙を作っています。
しかし、時間を利用して朝に枝を切ったり樹皮を剥いだりすれば、明日は米を買うお金が手に入るでしょう。私の家族と同じように、4 人の子供を成人まで育て、成長させ、勉強させることができたのは、論文作成という職業のおかげでもあります。
この仕事は私を救ってくれたのに、今はそれを支えることができないので悲しくて不安です。かつては村全体で100世帯以上がこの仕事に従事していましたが、現在は4世帯しか残っていません。労働者もまた、他の仕事ができない高齢者である。しかし若い世代はそれを知らないようです。
ハさんによると、焼き魚を包む、扇子、書道用紙、提灯などを作るなど、土紙を原料とする産業はたくさんある。しかし、原料(ニエットの木)の減少とともに、収入の低さが、人々が先祖伝来の工芸品に興味を持たない理由となっている。
「夫婦二人で一生懸命働いても、平均で15万ドンくらいしか稼げないと計算してみました。建設作業員の半日分の賃金にも満たない金額です。村の中には、紙を買う場所を探しに行き、村人のために製品を買いに戻ってくる人もいましたが、利益が出なかったため、しばらくするとやめざるを得なくなりました」とハ氏は語った。
夫がそう言うのを聞いて、ヴオン・ティ・ロアン夫人はため息をついた。「力のある者は建設作業員として働きに行くのだ。」若い世代は、学校に通う人は専攻や職業を選び、そうでなければ海外に出て働き、月に数千万を稼ぐでしょう。
「私の家族には4人の子供がいますが、誰もこの職業に就いていません。唯一、この仕事ができる娘は遠くに住んでいます。村でこの仕事をしている残りの3家族は皆高齢です。もしかしたら、私たちの世代が亡くなったら、私たちもこの職業をあの世に持っていくかもしれません…」とロアンさんは言いました。
ロアンさんによると、祖先の尊い職業が失われないように、今もその職業を営む人々はそれを誰とでも分かち合う用意があり、自分のために留めておこうという考え方を持っていないそうです。以前、ディエンチャウからこの職業を学びに来た人がいて、夫婦は喜んでその技術を継承しました。
「ゲアン博物館や民間団体が主催する体験交流会に参加しました。中には、私たちの家に来て工芸を学び、額縁を買って紙を母国に持ち帰った韓国人もいました。彼らは私たちに、様々なデザインの梵紙を試作してほしいと頼んできたのですが、どれもとても美しかったです」とロアンさんは語りました。
ギフォン村人民委員会のグエン・コン・アイン委員長は、紙作りは地元で長く受け継がれてきた伝統工芸だが、消えつつあると語った。 100世帯以上がこの仕事に携わっていたが、現在残っているのは4世帯だけだ。
その理由は、ヴィン市の再開発によりギフォンが中核地域となり、地価と産業の移行速度が急速に上昇したためである。かつてドーの木が生育していた地域はもう存在せず、ニエットの木も徐々に姿を消しつつあります。
「地元政府も先祖伝来の職業を非常に重視していますが、原材料が入手できなくなってしまったため、発展させるのは非常に困難です。私たちにできるのは、今もこの職業を営んでいる人々に、この仕事を続け、若い世代に受け継いでいくよう促すことだけです…」とアン氏は語った。
出典: https://www.baogiaothong.vn/mai-mot-lang-nghe-giay-do-doc-nhat-xu-nghe-19224122622183319.htm


![[写真] 建造物やシンボルを通して見る、国家統一50周年を迎えたホーチミン市](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/15/a224d0b8e489457f889bdb1eee7fa7b4)
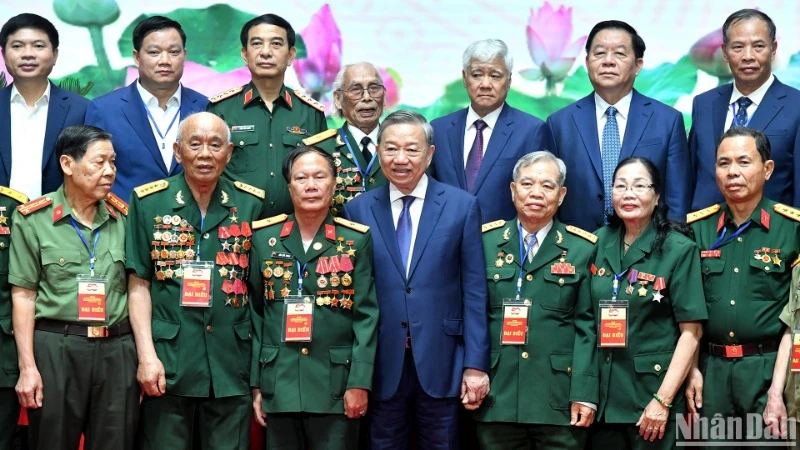


![[写真] 空軍、4月30日の記念日に向けて活発な訓練を実施](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/15/16fdec3e42734691954b853c00a7ce01)
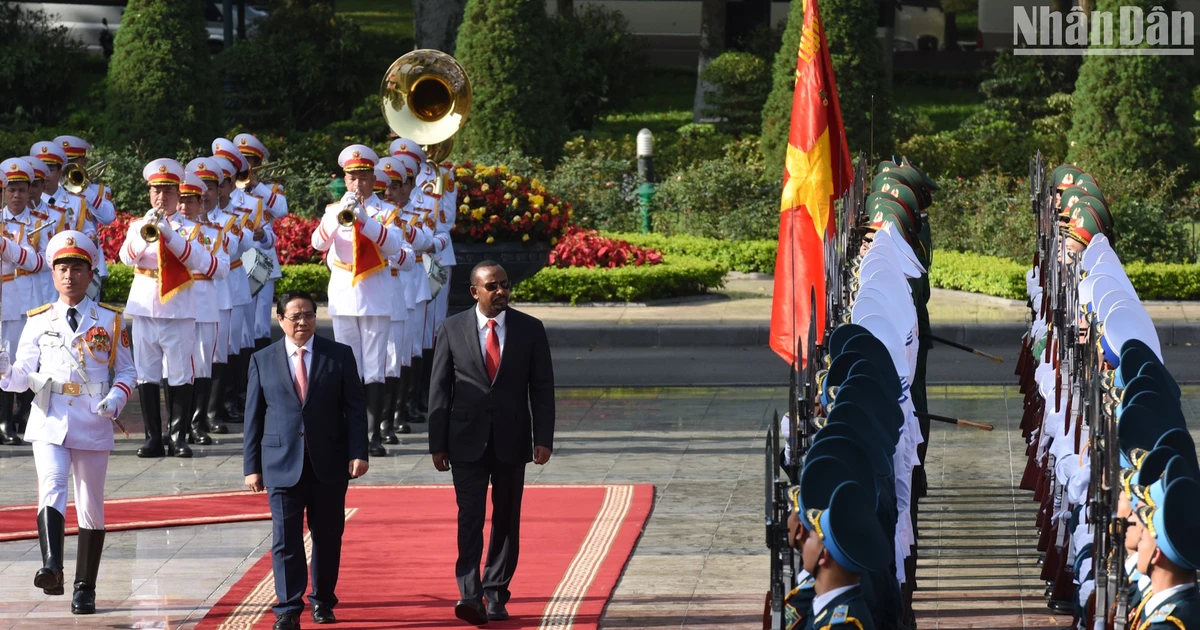











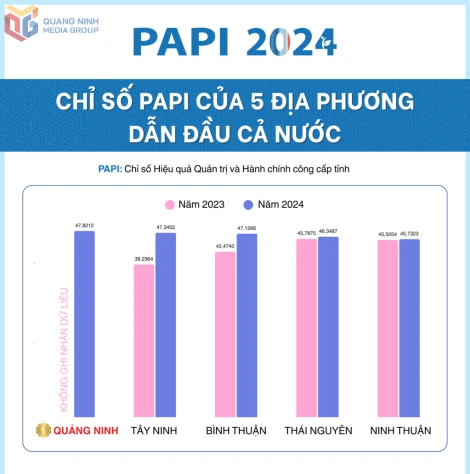


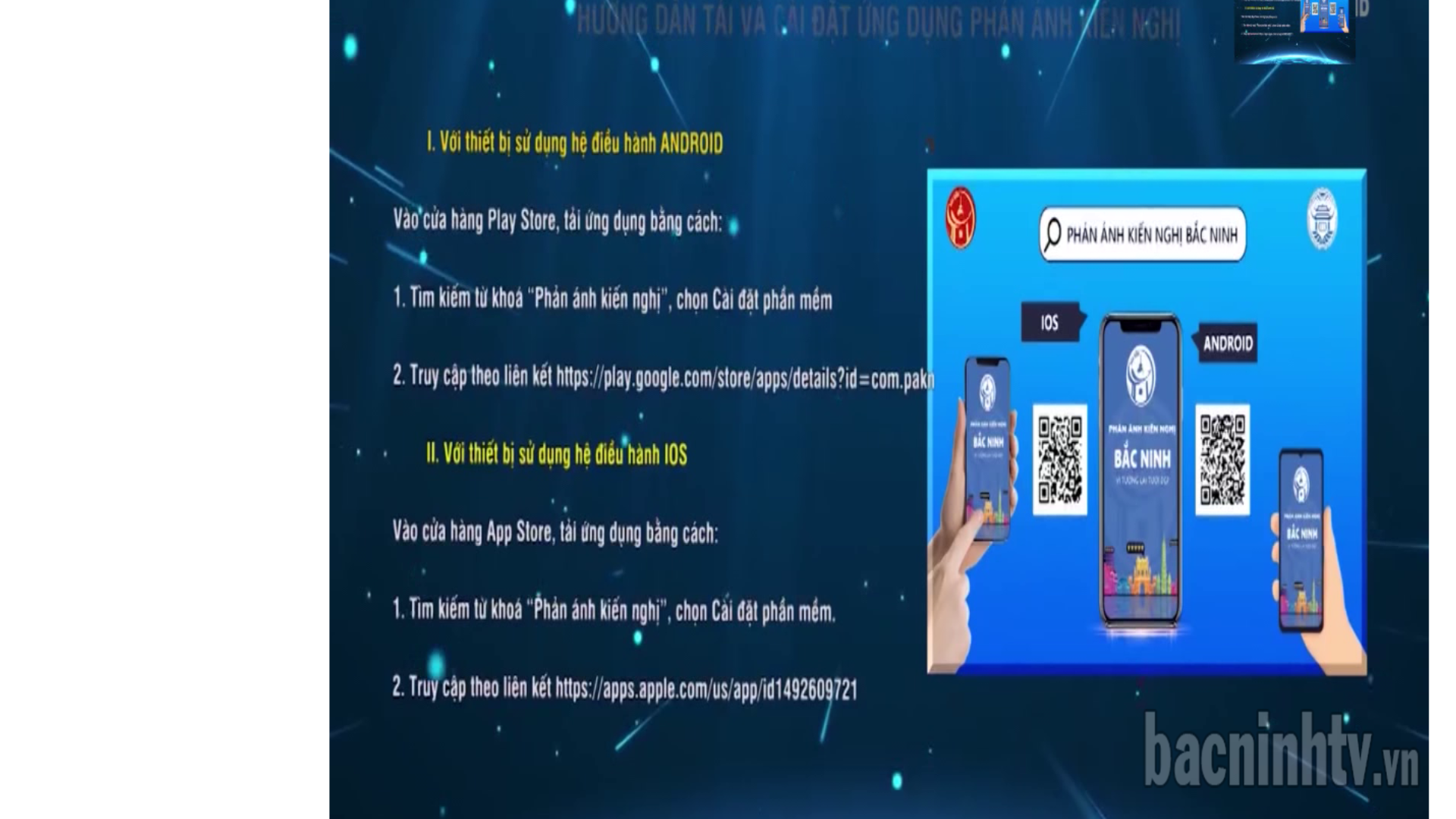


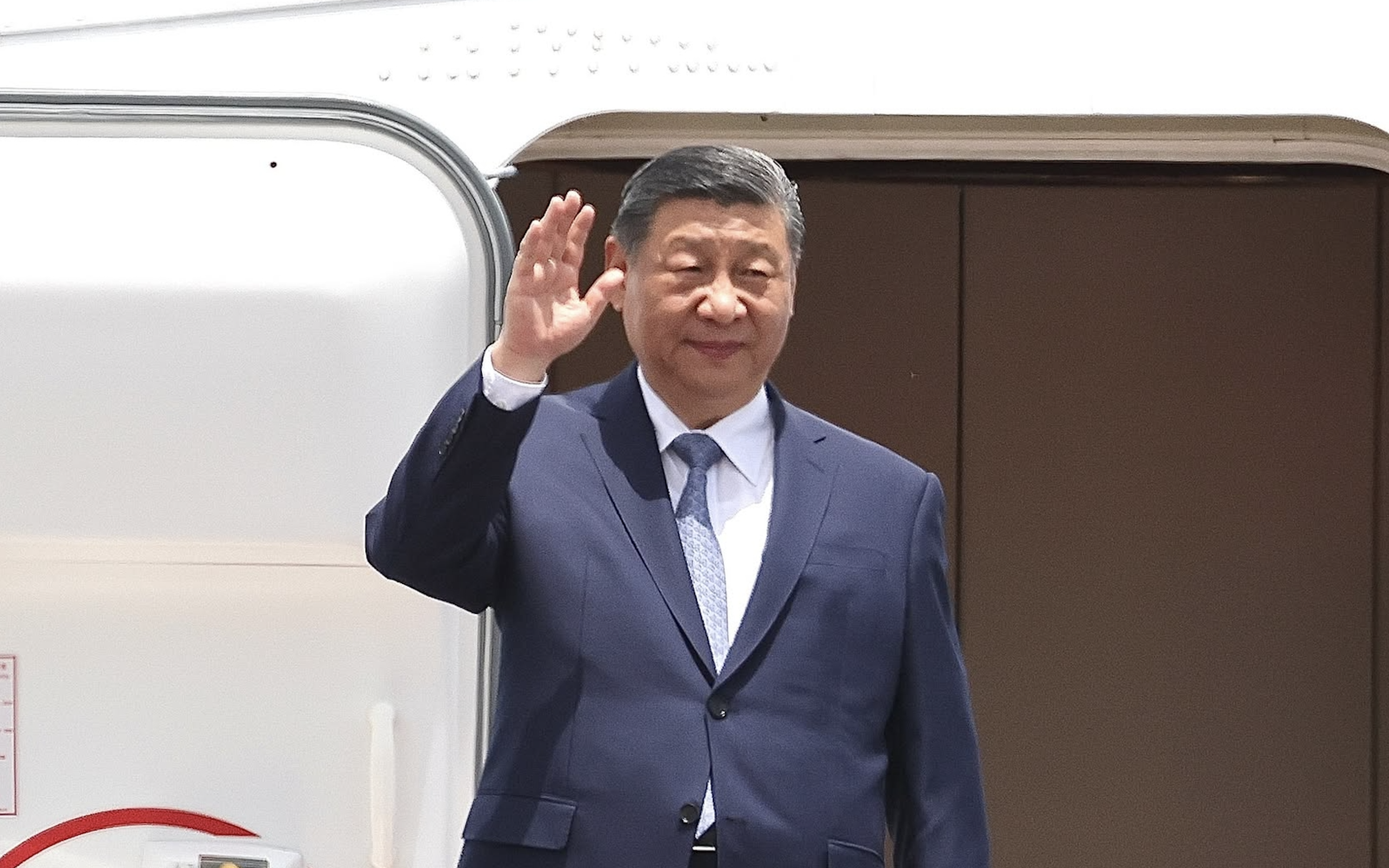







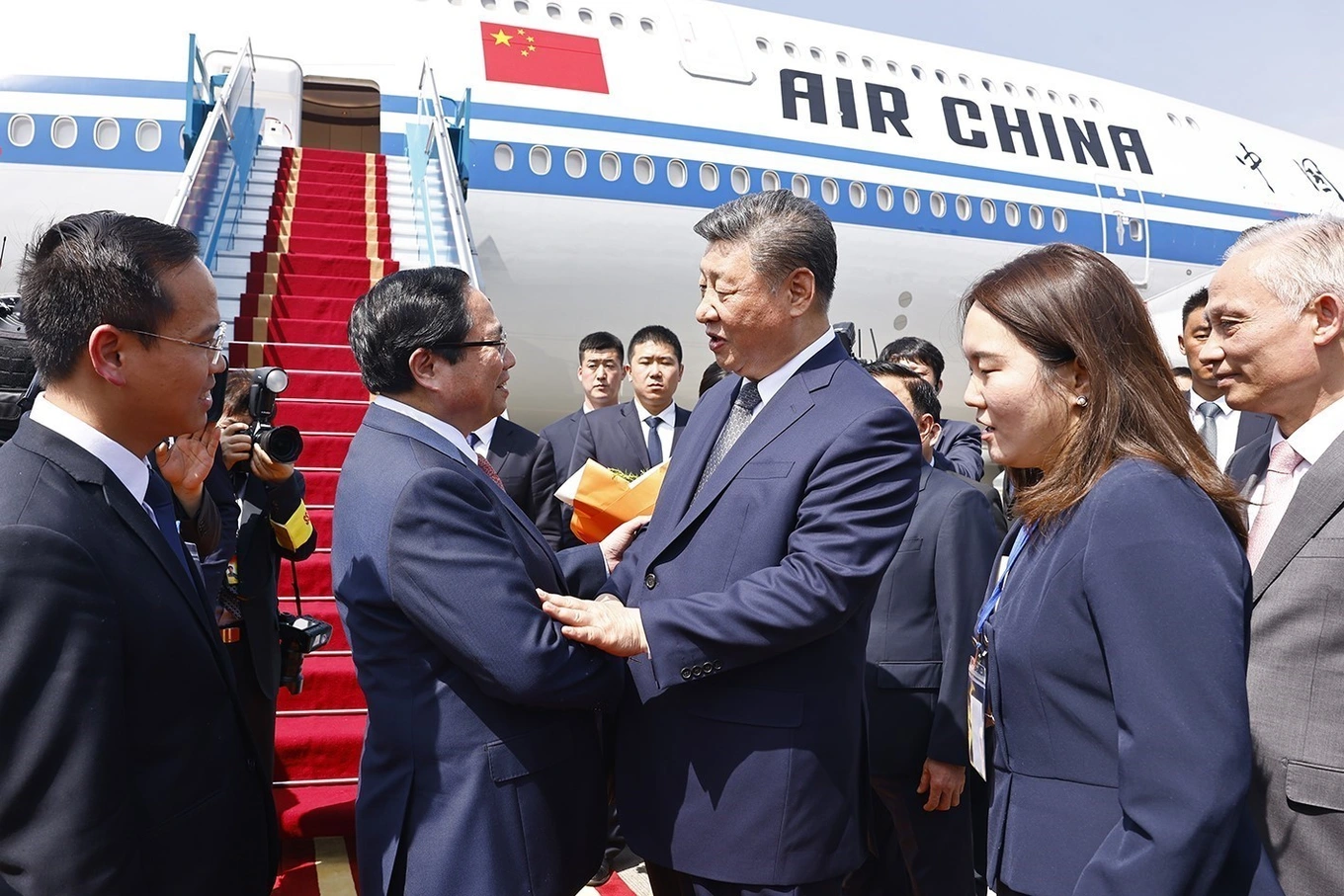








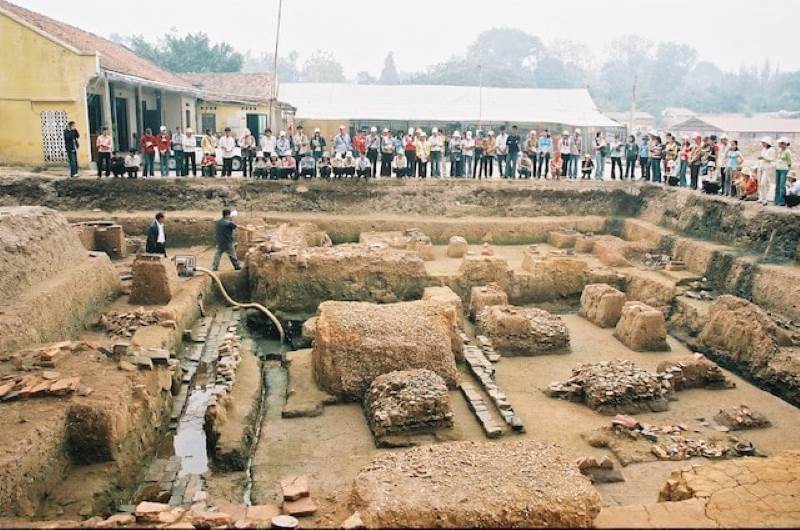






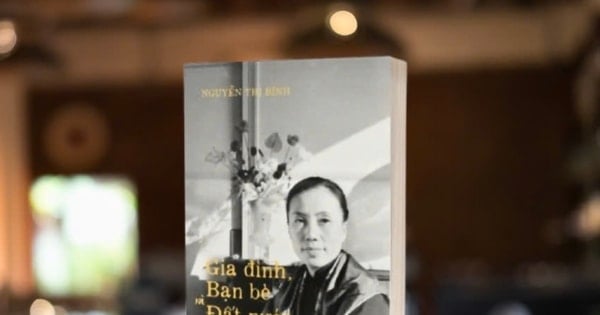

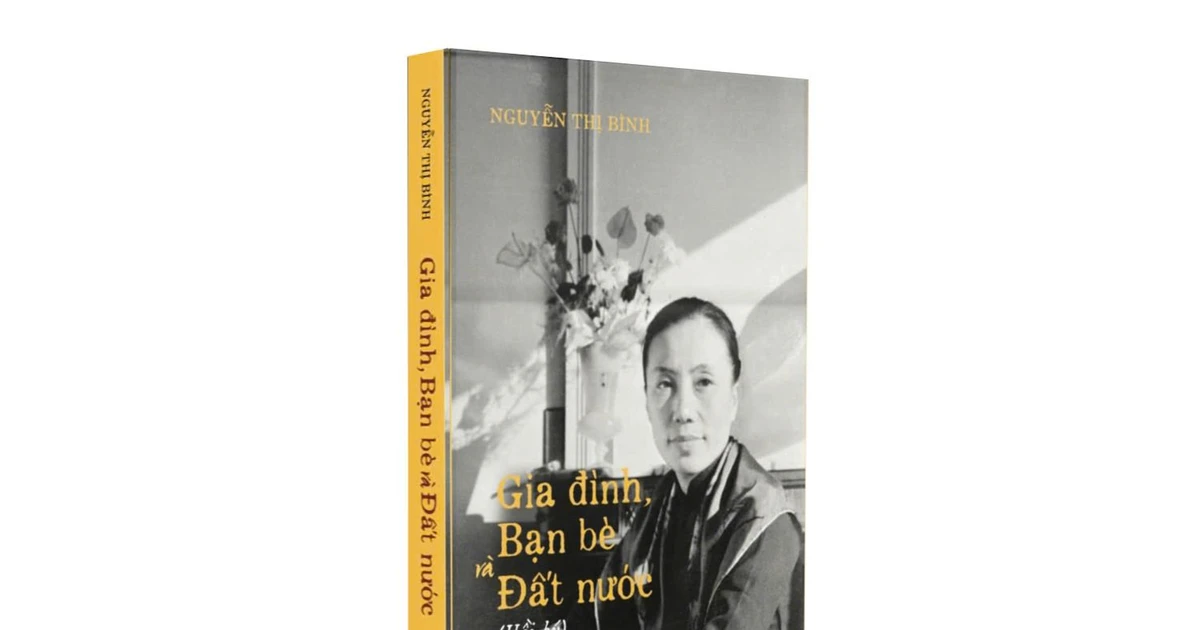
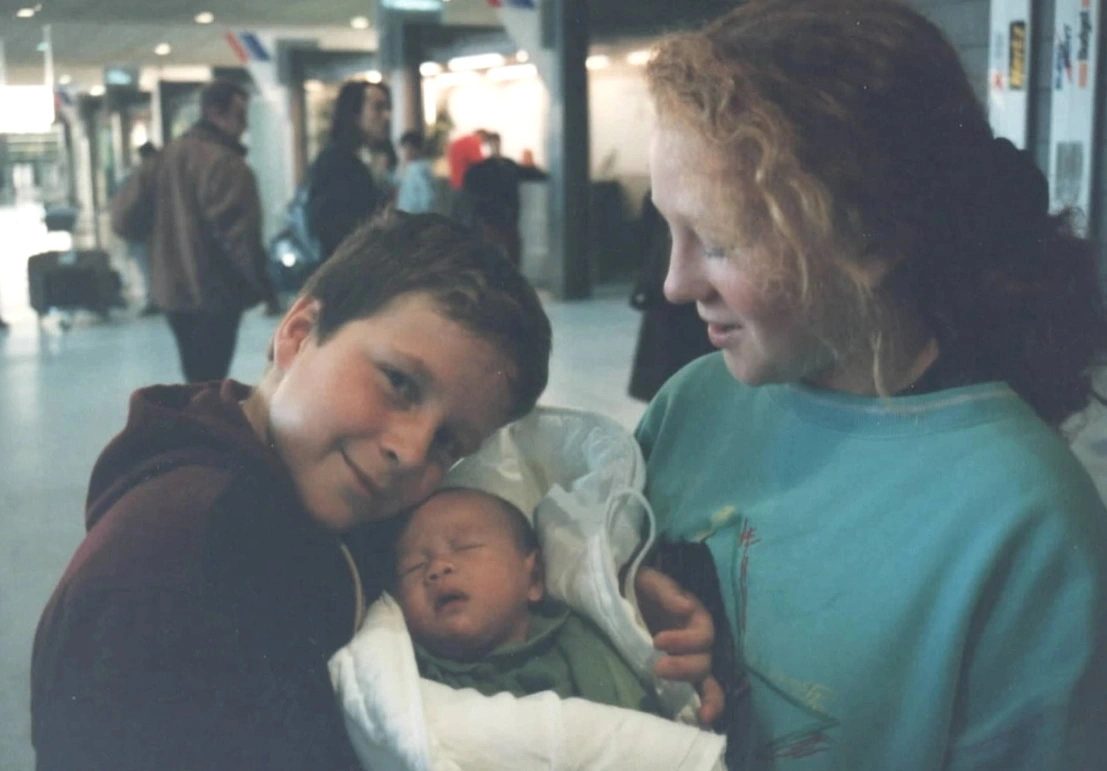



















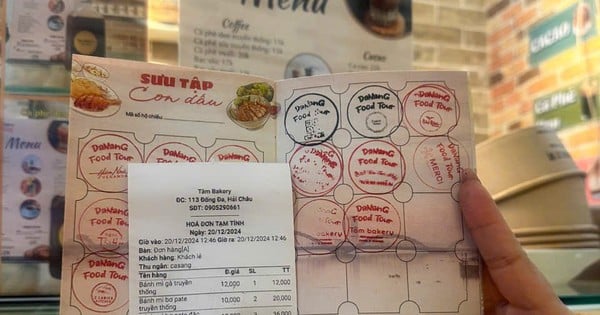

















コメント (0)