ちょうど80年前、ヤルタ会談が開催され、第二次世界大戦の終結だけでなく、米国とソ連の二極世界秩序の始まりを告げる出来事もありました。
 |
| 前列左から:1945年のヤルタ会談における英国首相ウィンストン・チャーチル、米国大統領フランクリン・ルーズベルト、ソ連書記長兼閣僚評議会議長ヨシフ・スターリン。(出典:米国国立公文書記録管理局) |
1945年2月4日から11日までクリミア半島のヤルタリゾートで開催されたヤルタ会談には、ソ連共産党書記長で閣僚会議議長のヨシフ・スターリン、米国大統領フランクリン・D・ルーズベルト、英国首相ウィンストン・チャーチルを含む、第二次世界大戦の連合国3カ国(「ビッグ3」)の指導者が一堂に会した。
この会合は第二次世界大戦が最終段階に入った頃に開催された。連合軍はヨーロッパで重要な勝利を収めており、枢軸国(ドイツ、日本、イタリア)の崩壊は時間の問題でした。しかし、世界の再編、戦利品の分配、戦後の永続的な平和を維持するための仕組みなど、大きな課題が残っています。
重要な合意
米国国務省歴史局によれば、ヤルタ会談では第二次世界大戦と戦後の世界の今後の進路に関して重要な決定が下された。
会議最終日(1945年2月11日)に歴史局が発表した共同声明には、ナチスドイツが滅ぼされたことが明記されていた。会議で最も重要な合意の一つは、ドイツをアメリカ、イギリス、フランス、ソ連の主要国が管理する4つの地域に分割することだった。これらの地域の管理と統制は、三大国の最高司令官から構成されるベルリンに本部を置く中央統制委員会を通じて調整された。
首脳らは、ファシズムを根絶し、ドイツを完全に武装解除し、防衛産業を破壊して軍事力の回復能力を制限し、戦争犯罪者を処罰し、ドイツに戦争被害の賠償金を支払わせる必要があることに同意した。
米国と英国は、ソ連と国境を接する東欧諸国の将来の政府はソ連政権に「友好的」であるべきであることに概ね同意し、ソ連はナチスドイツから解放されたすべての地域で自由選挙を認めると約束した。
一方、記事「チャーチル、ルーズベルト、スターリンはどのようにして第二次世界大戦を終わらせる計画を立てたのか?」によると、帝国戦争博物館のウェブサイト (iwm.org.uk) によると、ポーランドの将来の問題はヤルタ会談の特に焦点であった。
具体的には、「ビッグ3」の首脳は、ソ連とポーランドの国境を、第一次世界大戦後に提案された境界線であるカーゾン線まで西に移動させることで合意した。協議の結果、3大国が承認できる形で新しいポーランド臨時政府を設立するための条件について合意に達した。
さらに、ヤルタ会談は国際連合(UN)設立に向けた重要な一歩となりました。首脳らは当初、国連憲章と、当時の常任理事国5か国からなる安全保障理事会の構造と拒否権について合意した。
アジア地域では、米国務省歴史局が発行した「ソ連の対日戦争参加に関する協定」によれば、3カ国は、外モンゴル(モンゴル人民共和国)の現状維持、日露戦争(1904~1905年)以前の極東および千島列島における権利のソ連への返還を条件に、ソ連が日本軍国主義との戦いに参加することを約束する議定書に署名した。
平和財団?
ヤルタ会談では、「ビッグ3」が共通の決意をもって戦後の世界平和を維持・強化し、「すべての国の人々が恐怖や欠乏なく、自由に一生を送れることを保証」するという決意を再確認したが、各首脳は戦後ヨーロッパの秩序再建について独自の考えを持って会談に臨んだと会談のプレスリリースには記されている。
ノースカロライナ大学ヨーロッパ研究センター(CES)が出版した「第二次世界大戦の終結とヨーロッパの分断」と題する論文によると、ルーズベルト米大統領はソ連が日本の軍国主義との戦いに協力し、国連に加盟することを望んでいた。英国のチャーチル首相は、中央・東ヨーロッパ、特にポーランドにおける自由選挙と民主的な政治を求めた。
一方、スターリン書記長は、ソ連が東欧と中央ヨーロッパでの影響力を拡大することを望み、それが連邦国家の防衛戦略の重要な要素であるとみなしていた。彼の姿勢は非常に強硬だったため、1945年から1947年まで米国国務長官を務めたジェームズ・F・バーンズ(1882年-1972年)は次のようにコメントした。「問題はロシア人に何をさせるかではなく、何を説得できるかだ。」
そのため、ヤルタ会談は緊張した激しい雰囲気の中で行われました。しかし、最終的な決定は、ソ連とアメリカの二大超大国間の合意と支配の後に行われました。
この新しい秩序の中で、ソ連は社会主義国家の存続と発展を守り、日露戦争(1904-1905)で失った領土を回復し、同時にヨーロッパとアジアでの影響力を拡大し、国の周囲に安全帯を築きました。米国は新秩序の中で西欧列強と日本を支配し、深い影響を与え、国際情勢を支配し、徐々に「世界覇権」の野望を実現してきました。
歴史研究局によれば、ヤルタ協定に対する当初の反応は祝賀的なものだった。ルーズベルト大統領は、他の多くのアメリカ人と同様、これを米国とソ連の戦時協力の精神が戦後も維持される証拠だとみなした。
当時、タイム誌は「『ビッグ3』が戦争だけでなく平和時にも協力できる能力についてのいかなる疑念も、今や払拭されたようだ」と断言し、元国務長官のジェームズ・F・バーンズ氏は「英国、ソ連、アメリカの友好の波は新たな高みに達した」とコメントした。
ヘンリー・キッシンジャー元米国務長官(1923年~2023年)は、多くの複雑な要素があったにもかかわらず、ヤルタ会談を同盟国の指導者、特にルーズベルト大統領による優れた外交戦略として称賛した。彼によれば、ヤルタ会談は実践的な協力の結果であり、戦後の安定を確保するために必要だったという。
ヤルタ会談の成功は、3大国がそれぞれの利益を維持しながら共存し、主要な問題を管理できたことにある。
冷戦の専門家で、現在はイェール大学(米国)の軍事・海軍史教授であるジョン・ルイス・ガディス氏は、著書『米国と冷戦の起源 1941-1947』の中で、ヤルタ会談は戦争が終結に向かう中で同盟国間の協力関係を維持する上で重要な一歩であったと述べている。
しかし、米国務省歴史局は、この「同盟」感情は長くは続かなかったことを認めた。 1945 年 4 月 12 日のルーズベルト大統領の死去に伴い、ハリー・S・トルーマンが第 33 代アメリカ合衆国大統領に就任しました。1945 年 4 月末までに、新政権は東ヨーロッパと国連における影響力をめぐってソ連と対立していました。
ここから、ソ連の協力不足を懸念した多くのアメリカ人が、故ルーズベルト大統領のヤルタでの交渉のやり方を批判し始めた。ソ連が重大な譲歩をしたにもかかわらず、今日に至るまで多くの人が、彼が東ヨーロッパをソ連に「引き渡した」と非難している。
英国の歴史家AJPテイラー(1906-1990)は、著書『1914-1945年の英国史』の中で、ヤルタ会談は「分裂したヨーロッパと不安定な世界」を残したと述べています。
ガディス教授もこの見解に賛同しており、ソ連が東ヨーロッパで影響力を拡大することを認めた決定が、中央ヨーロッパと東ヨーロッパを大陸の他の地域から隔てる「鉄のカーテン」の形成と、1947年の冷戦の始まりを促したと主張している。
ロシア側では、歴史家でソ連外交官のヴァレンティン・ファリン氏(1926年~2018年)が2015年にロシアのニュースサイト「トップウォー」のインタビューで、ヤルタ会談は古代以来の国民にとって最高の機会だったと評価した。
彼は、1945年3月1日にルーズベルト米大統領が米国、英国、ソ連間のヤルタ協定について議会で行った演説を引用した。「それは大国間の平和でも小国間の平和でもない。」それは全世界の共通の努力に基づく平和でなければなりません。」しかし、ファリン氏によれば、ルーズベルト大統領が描いた世界はワシントンの反対派の期待に応えず、「ソ連と米国の協力関係が崩壊する恐れがある」というリスクをもたらしたという。
スターリン書記長もヤルタ会談でこの問題について警告し、「危険な意見の相違が生じることは許されない...しかし、あと10年かそれ以下で終わるだろう」と宣言した。私たちが経験してきたことすべてを経験していない新しい世代がやって来て、おそらく私たちとは違った見方をするようになるだろう。」
そして明らかに、連合国はヤルタ会談の関係を最後まで維持することができず、わずか2年後にアメリカとソ連という2つの超大国の間で冷戦が勃発した。
[広告2]
出典: https://baoquocte.vn/hoi-nghi-yalta-cuoc-gap-go-quyet-dinh-van-menh-the-gioi-303400.html





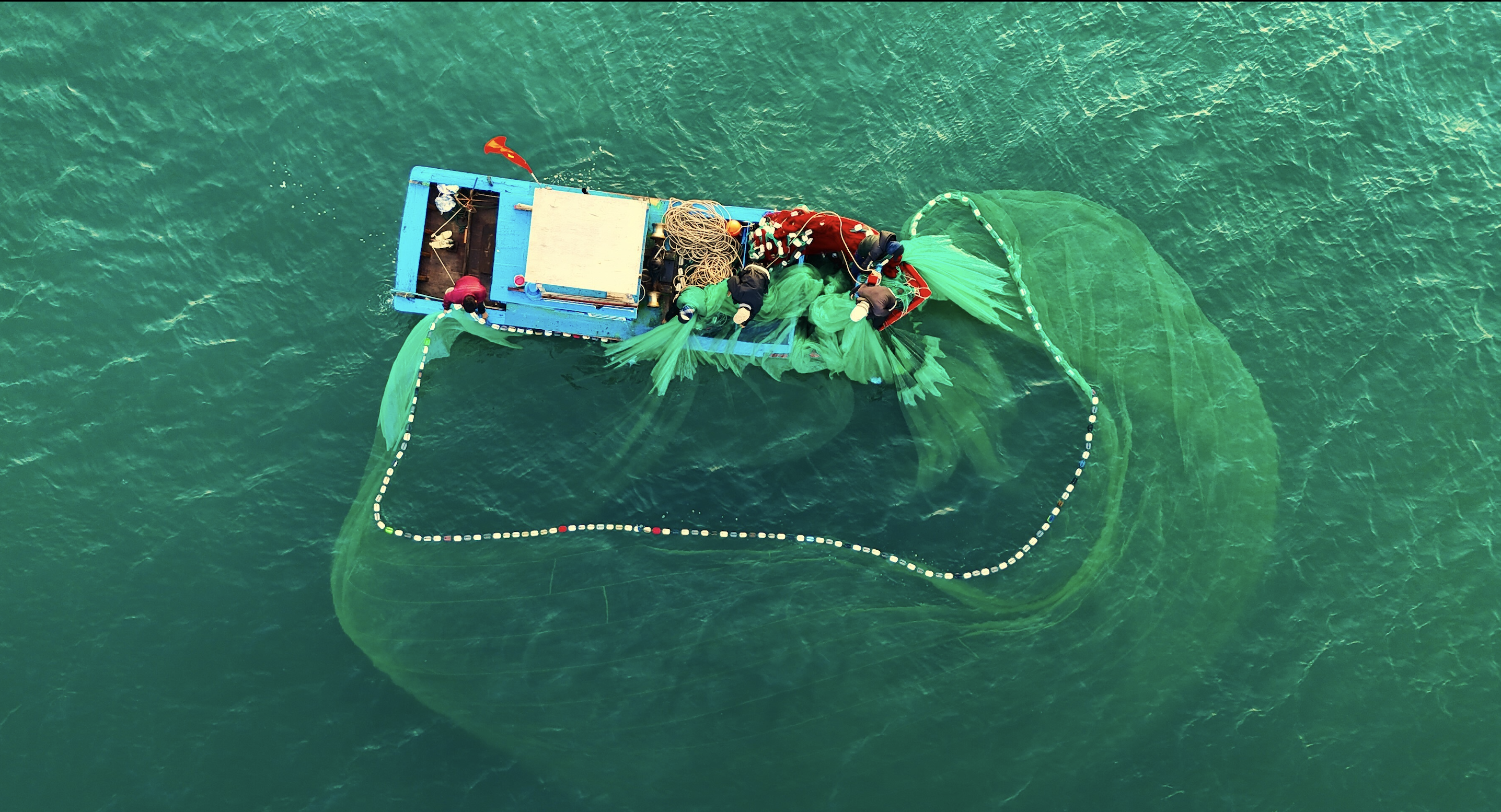






























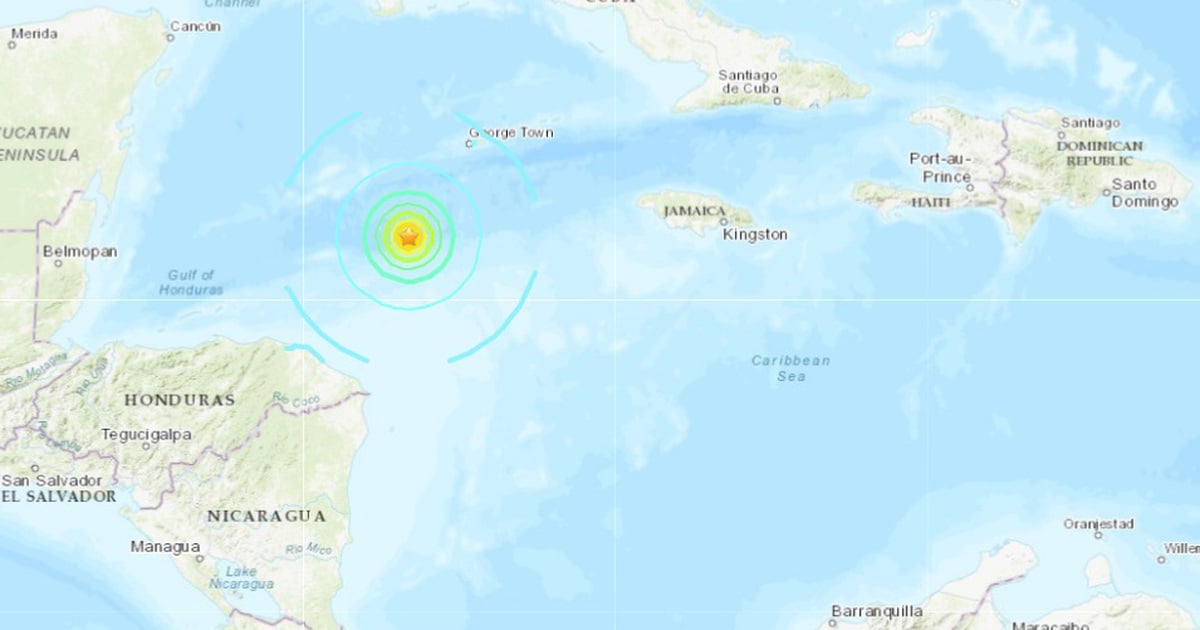





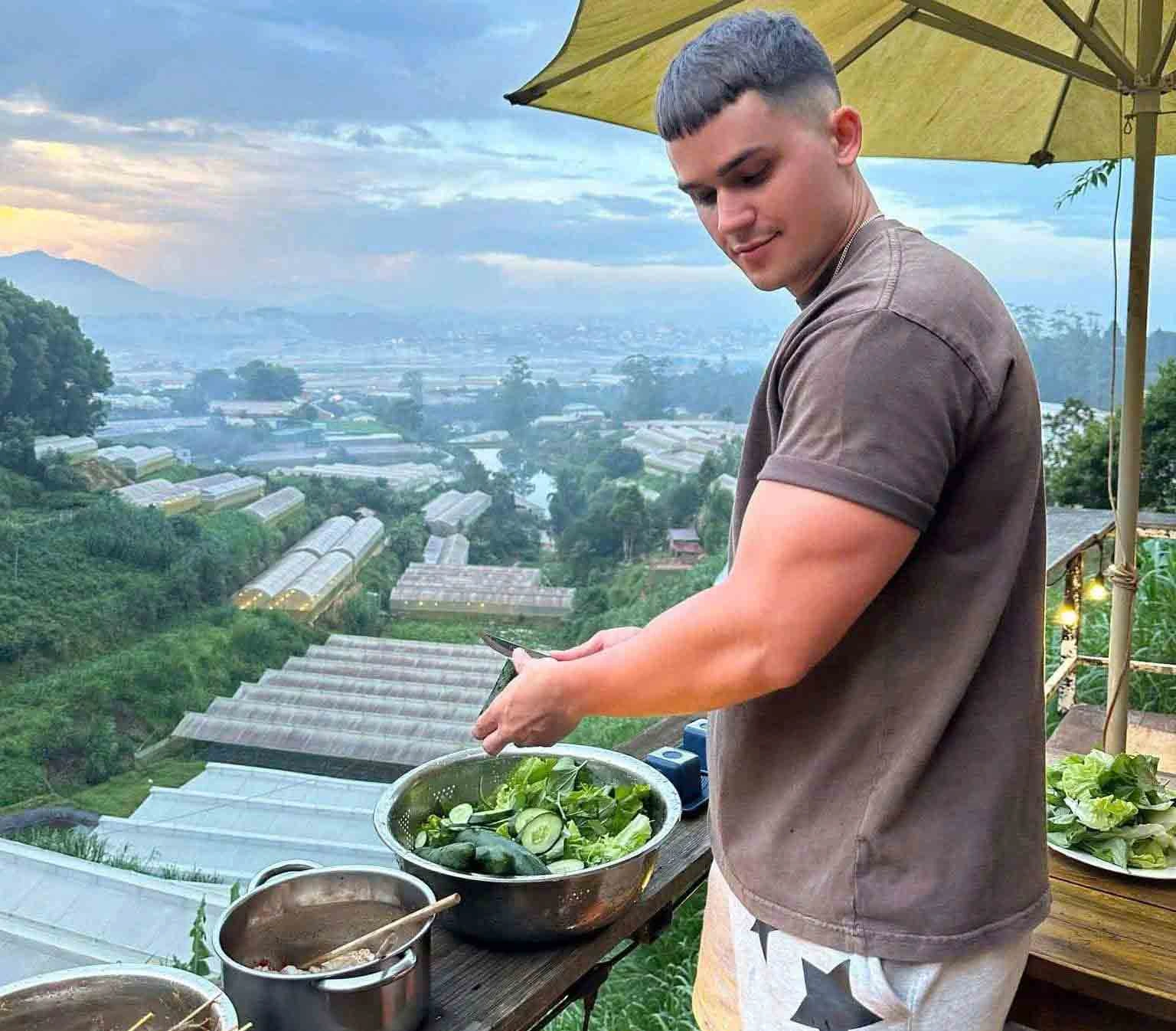








コメント (0)