現在、年金受給の条件である社会保険料の納付期間が20年というのは長すぎると考えられており、従業員が加入して長期にわたって年金を受給する意欲を減退させています。その結果、多くの従業員は社会保険をすぐに脱退するだけの忍耐力がなく、特に、これまで長い間社会保険を支払ってきたにもかかわらず、退職時に労働能力を失い収入がなくなった人々にとっては、将来の生活に影響を及ぼしました。
2024年社会保険法は国会で可決され、年金条件の調整や一時金の増額など多くの重要な内容を伴い、2025年7月1日から正式に施行されます。従業員を社会保険制度に留め、生活を保障するために、多くの重要な内容を盛り込んだ「社会保険法 2024」が国会で可決され、2025年7月1日から正式に施行されました。年金条件の調整や一時金の増額など。
2025年7月1日以降の退職時に一時金を受け取るための条件現行の2014年社会保険法によれば、年金率75%に該当する年数を超えて社会保険を支払った従業員は、退職時に年金に加えて一時金も受け取ります。したがって、現行規定では一時金を受け取るための条件は、年金率75%に相当する年数よりも長い社会保険料納付期間があることです。この補助額は、年金支給率75%に相当する年数を上回る社会保険料納付年数に基づいて算出されます。社会保険料の年額は、社会保険料の平均月収の0.5か月分として計算されます。ただし、2024年社会保険法により、2025年7月1日からこの規制は調整されます。具体的には、2024年社会保険法(2025年7月1日発効)第68条第1項の規定に基づき、社会保険の納付期間が35年以上の男性従業員、社会保険の納付期間が30年以上の女性従業員は、退職時に年金に加えて一時金も受け取ることができます。したがって、2025年7月1日から、退職時に一時金を受け取るための条件は、より長い社会保険料納付期間(男性労働者の場合35年)を有することです。女性労働者の場合は30年。
 一時金の額も変更され、2024 年社会保険法第 68 条第 2 項に規定されています。
一時金の額も変更され、2024 年社会保険法第 68 条第 2 項に規定されています。
一時金の額も変更され、2024年社会保険法第68条第2項に2つのケースに分けて規定されています。 まず、従業員が年金受給資格を有し、年金受給手続きを完了している場合、一時金は、法律で定められた定年まで、社会保険法第68条第1項の規定を上回る納付年数ごとに、社会保険料の基礎となる平均給与の0.5倍で計算されます。この場合、一時金の支給額は、2014年社会保険法の現行規定と同じです。次に、従業員が年金受給資格を有しながらも社会保険料の支払いを継続している場合、支給額は、規定の年数(法律による定年退職年齢に達した時点から退職し年金給付を受ける時点まで)を超える支払い年数ごとに、社会保険料の支給基準として使用される平均給与の2倍に相当します。
従業員が年金受給資格者でありながら社会保険料を納付し続けている場合、補助額は、所定納付年数を超える納付年数ごとに社会保険料納付の基礎となる平均給与の2倍に相当します。
この場合、一時金は2014年社会保険法に基づく現在の給付水準の4倍になります。
2025 年 7 月 1 日以降の退職時の一時金レベルの計算方法労働傷病兵社会省は、一時金の計算方法について次のようにガイドラインを示しています。 例: D さんは通常の労働条件で働いており、退職年齢の時点で 38 年間の社会保険料を支払っています。しかし、Dさんは年金を受給するために退職せず、年金を受給するために退職するまでさらに3年間働き続け、社会保険料を納めました。 Dさんは退職して年金を受け取った時点で、合計41年間の社会保険料を支払っていました。したがって、D 氏は年金に加えて、次のように計算される一時金も受け取る権利があります: - 退職年齢の前の 3 年間の社会保険料の支払期間が 35 年を超え、各年は社会保険料の基準として使用される平均給与の 0.5 倍に相当します: 3 年 x 0.5 = 1.5。 - 退職年齢から35年を超えて社会保険料を支払った期間が3年間の場合、1年あたりの保険料額は、社会保険料の基準となる平均給与の2倍に相当します。つまり、3年×2=6です。したがって、D氏は、退職時に社会保険料の基準となる平均給与の7.5(1.5+6)倍に相当する一時金を受け取る権利があります。出典: https://tienphong.vn/tu-172025-tro-cap-khi-nghi-huu-tang-gap-4-lan-muc-cu-post1697858.tpo

 一時金の額も変更され、2024 年社会保険法第 68 条第 2 項に規定されています。
一時金の額も変更され、2024 年社会保険法第 68 条第 2 項に規定されています。



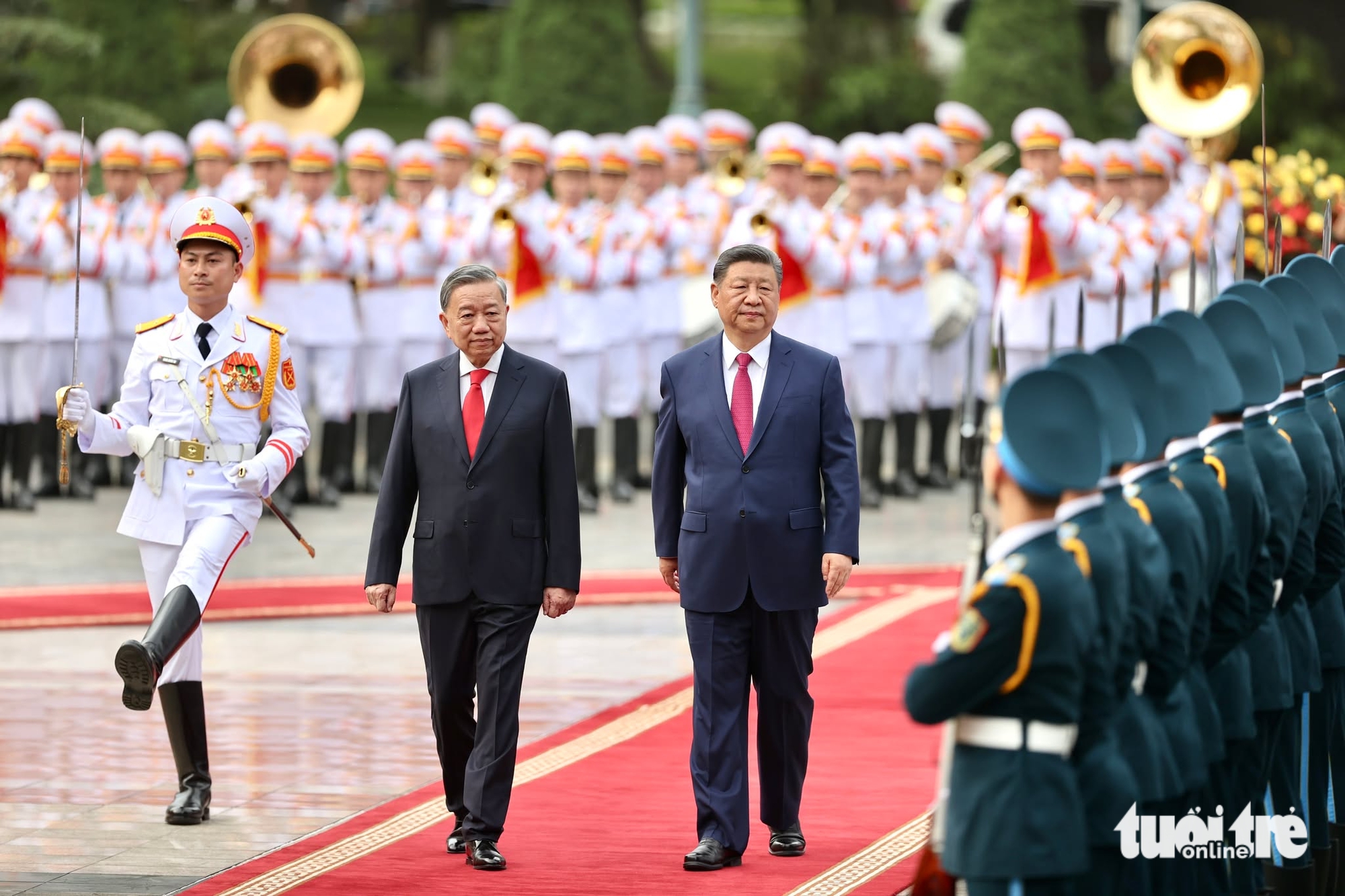
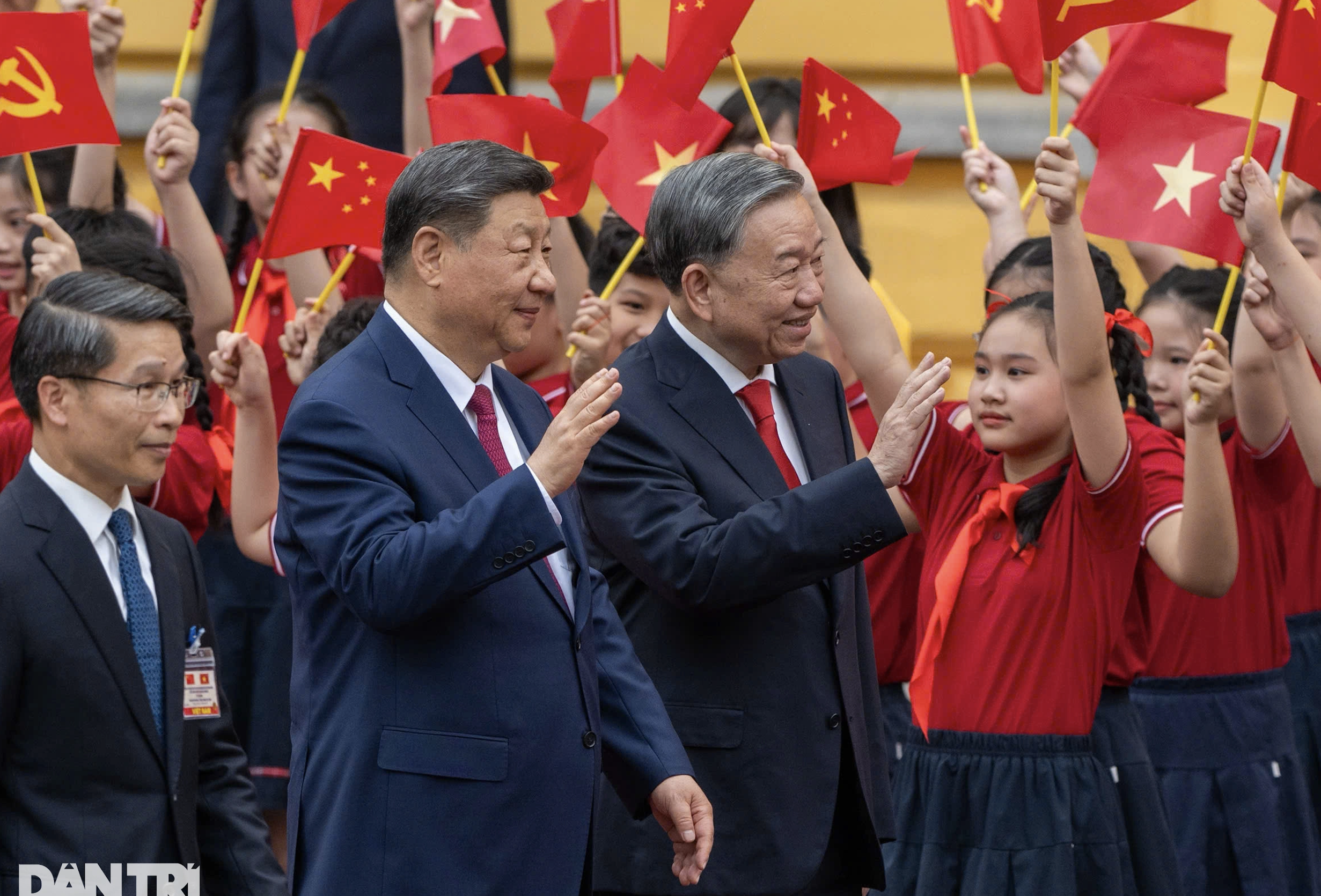
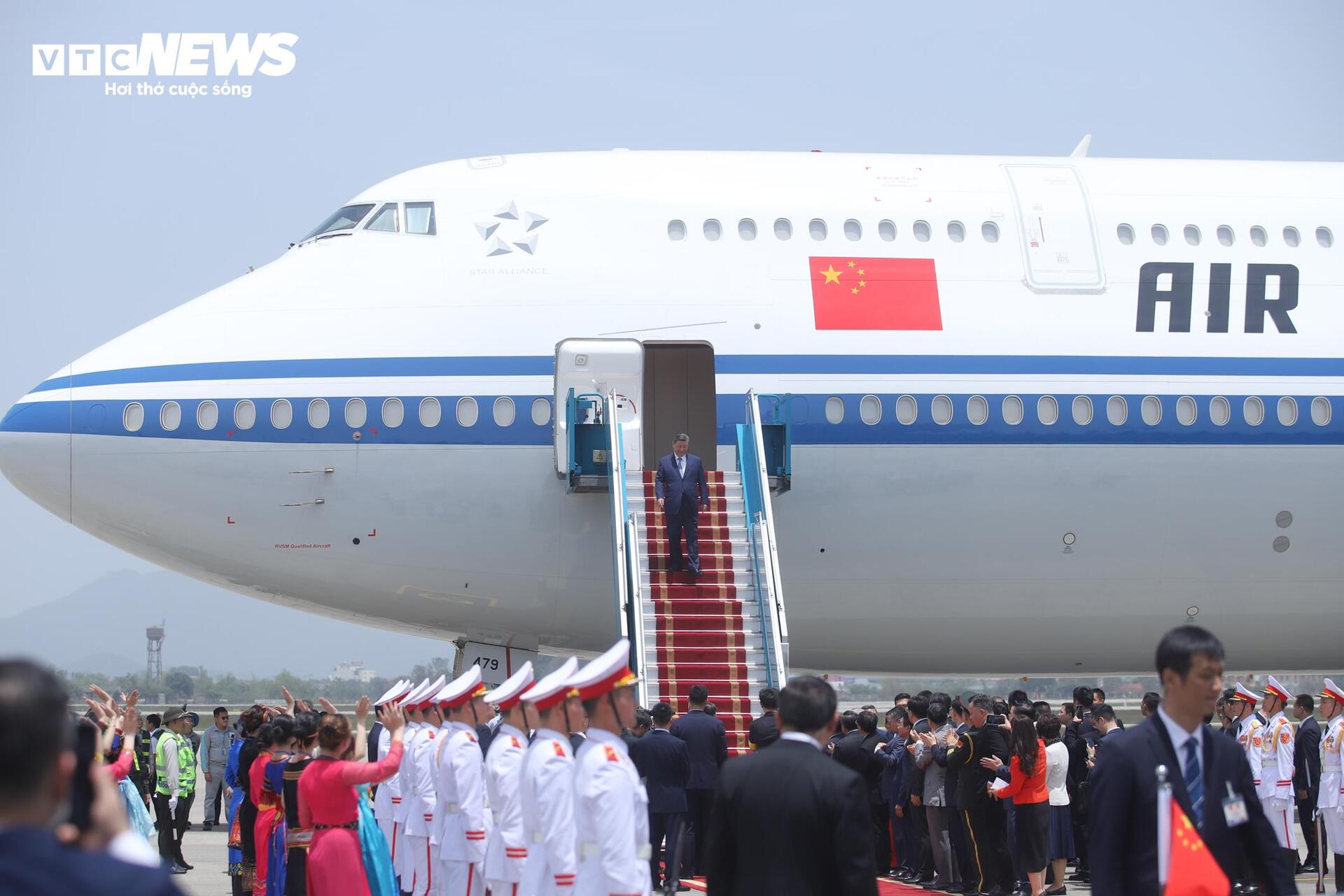

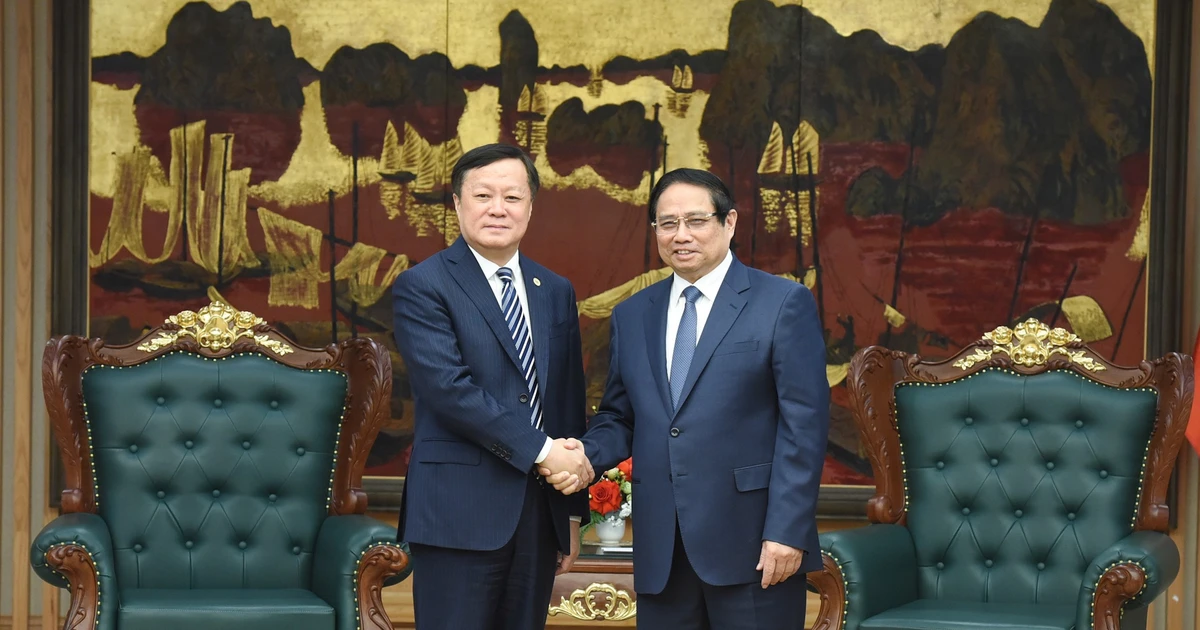
















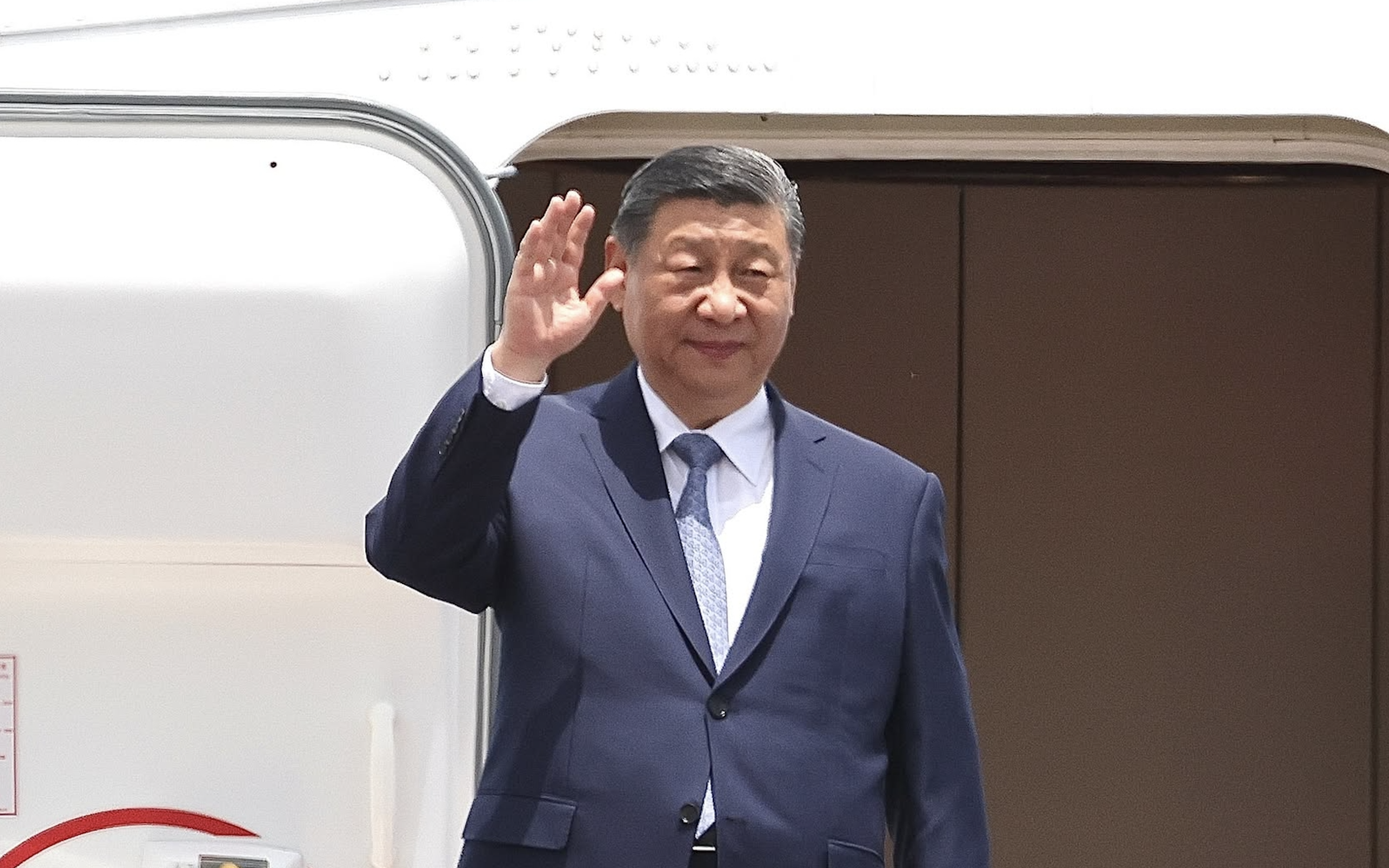









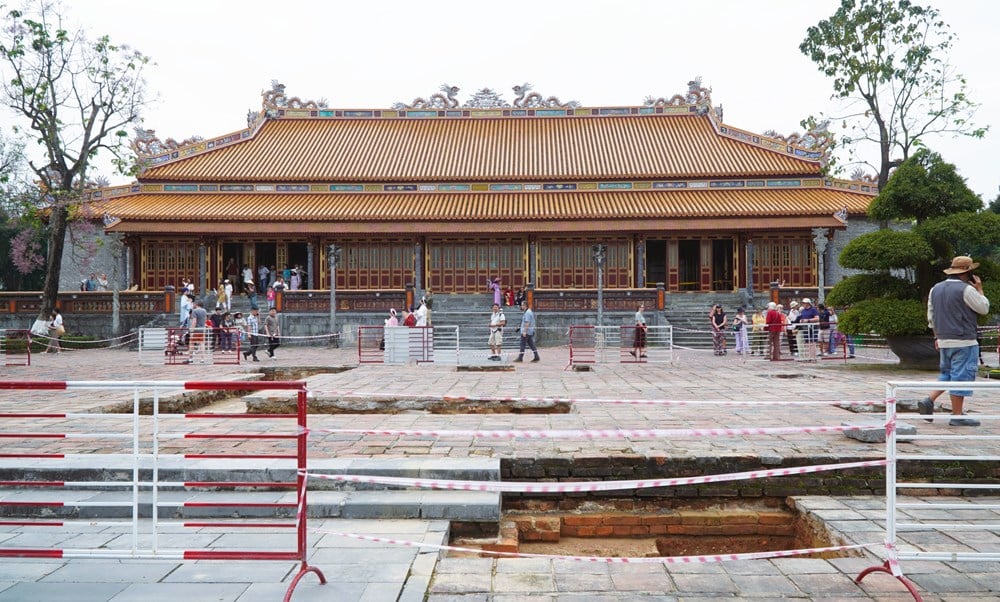


















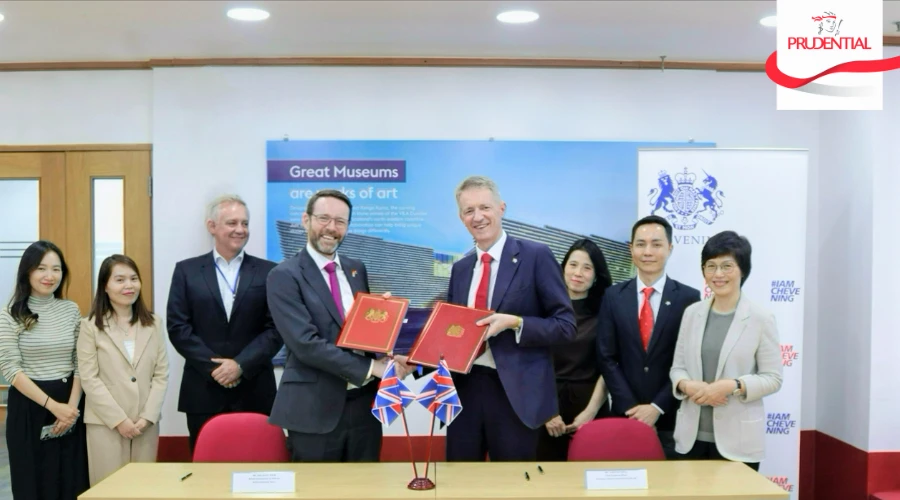








































コメント (0)