中央執行委員会の給与政策改革に関する決議第27号によると、7月1日から、教員の新しい給与体系には、基本給(給与基金総額の約70%を占める)、手当(給与基金総額の約30%を占める)、追加ボーナス(手当を除く年間給与基金総額の約10%)が含まれることになる。
全国的に給与改革が実施されるまで2カ月以上あるが、教員の新しい給与の算定方法案に関する情報はまだない。

7月1日から、教員の給与は給与改革方針に従って計算されます。 (図)
教育分野で約25年間働いてきたタンタンA小学校(ビンフオック)の教師、ブイ・ティ・ニョンさんは、教師の給与が最高額のグループに入る可能性があるという情報を得て喜んだ。
「現在、教師の収入は依然として低く、生活費を賄うにも足りず、職務に見合った額ではありません。そのため、多くの教師がより良い収入を求めて職を辞しています。教師の給与が他の職業の平均と比べて最も高いグループに入っていると聞いたとき、同僚たちと私はとても喜びました」とニョンさんは語りました。
給与の引き上げは、教育分野の労働者の努力に対する認識と評価を示す重要な前進です。教師にとって、給与の増加は仕事に安心感を持ち、生活の心配をせずに職業を続ける動機にもなります。
ブイ・ティ・ニョンさんは、昇給の喜びの一方で、給与改革が行われると勤続手当がなくなるのではないかとも懸念している。
「私も他の多くの同僚と同じように、7月1日から給与改革について初めて知りましたが、新しい給与計算方式についてはまだ詳細を知らされていません。しかし、勤続手当が廃止されれば、私のように長年の経験を積んだ教員の給与は不利になるのでしょうか?」とノンさんは疑問を呈した。
フック・カン中学校(タイビン省)の教師ファム・ティ・ニャンさんは、勤続手当がなければ不利になるのではないかと懸念している。なぜなら、勤続手当は給与を計算する指標であるだけでなく、教師が教職に就いた期間を示すものでもあるからだ。
「給与改革後、多くの若い教師が収入が増えることを喜んでいる一方で、勤続年数の長い教師の中には、改革後に収入や福利厚生が保証されるのかどうかわからないため不安を抱く者もいる」とニャン氏は述べ、勤続手当は非常に重要で、これが教師が教職にとどまり、努力を続けるための動機付けになると付け加えた。教師は、この手当が廃止されれば、長年教師を務めている人たちは多くの不利益を被ることになるだろうと述べた。
「低地でも高地でも、幼稚園教諭の仕事は極めて過酷です。朝6時から午後5時半まで、あるいは仕事が終わるまで、ずっと教室に通わなければなりません。この年齢の子どもたちは自分で自分の面倒を見ることができないので、教諭は愛情と献身、そして情熱をもって子どもたちを教え、育てなければなりません」と、ホアマイ幼稚園(ソンラ県イエンチャウ)のレ・ティ・トアン園長は語った。
2023年7月には基本給が149万ドンから180万ドンに上がり、教師たちに大きな喜びをもたらしました。 7月1日から新しい給与政策が実施されるまでは、教師たち、特に幼稚園の教師たちが楽しみにしている時期です。
彼女は、新しい給与政策によって教師たちが給料だけで生活できるようになり、食べ物やお金についてあまり心配する必要がなくなり、自分の仕事に時間と精神を集中できるようになることを期待している。
ファム・ティ・タン・トラ内務大臣によれば、現在、職業別の給与や給与手当を含む教師の総収入は他の職業に比べて向上している。しかし、内務大臣は、教員の給与は特殊性に比べてまだ低いことも認め、今後、給与改革を実施する際には、教員の給与を行政キャリアシステムにおける最高の給与水準と表に配置することを優先すると断言した。
内務省の情報によれば、教師の給与は、仕事の複雑さが同じであれば同じ給与になるという原則に従って調整される。複数の職務を担い、困難で複雑な業務を遂行する教師には、適切なインセンティブが与えられる。
大臣はまた、内務省が教育訓練省と連携し、教員の給与(手当を含む)が職務要件や役職に応じて増加し、幹部、公務員、公務員の一般的な給与水準に沿った増加を確保し、教育部門に対する優遇措置も示すと述べた。
決議第27号では、年功手当の廃止に加え、指導的地位手当、政党および社会政治組織の活動手当、公共サービス手当、有害物質および危険物手当も廃止し、基本給に含めることになっている。併せて、兼務手当、永年勤続教員の枠を超えた勤続手当、地域手当、職務責任手当を引き続き適用する。移動手当
通常よりも高い労働条件が課され、教育や訓練を含む国の適切な優遇政策が適用される職業や職務に就く公務員や公務員に適用される職業手当、職業責任手当、危険有害性手当(総称して職業手当という)を組み合わせたもの。
特に、決議第27号においては、旧給与から新給与への転換額が現行給与を下回らないようにしなければならないとの考え方も明記されております。
[広告2]
ソース



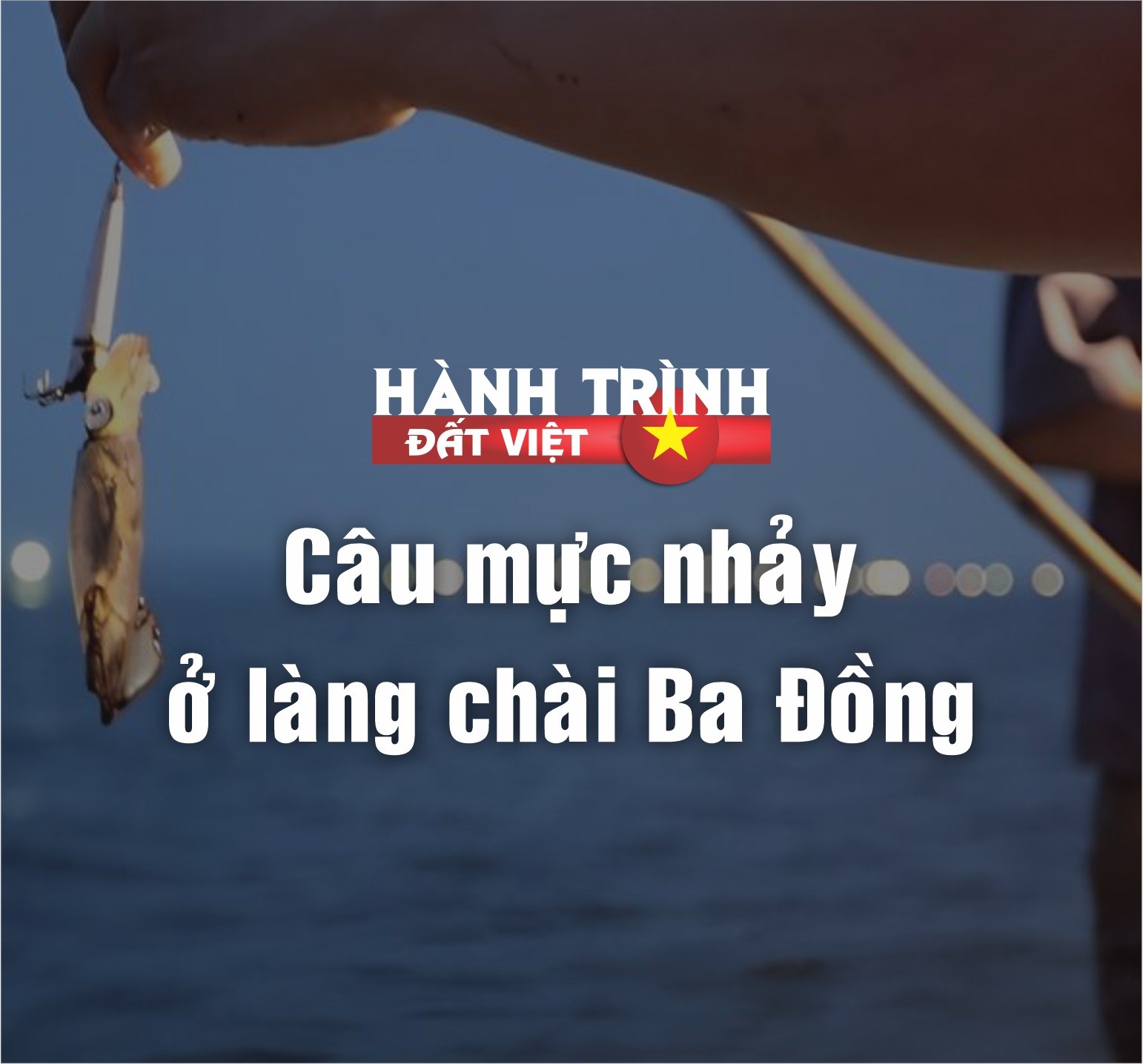

![[写真] ト・ラム事務総長がベトナム駐在フランス大使オリヴィエ・ブロシェ氏を接見](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/17/49224f0f12e84b66a73b17eb251f7278)
























































![[動画] Viettelがベトナム最大の海底光ケーブルラインを正式に運用開始](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/17/f19008c6010c4a538cc422cb791ca0a1)
















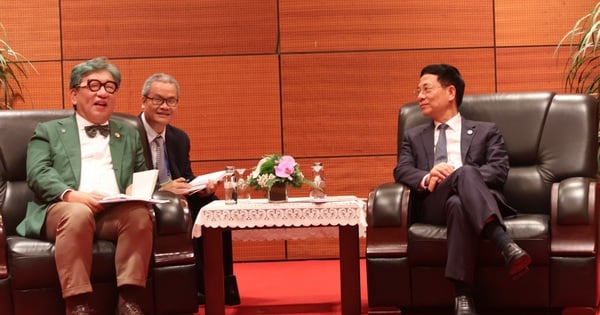




















コメント (0)