日本のメディアは、1月1日に石川県で発生した地震による行方不明者が8日午前9時(現地時間)時点で323人に増えたと報じた。
一方、 NHKによると、マグニチュード7.6の地震による死者数は168人に上った。石川県が発表した最新のリストによると、地震で最も大きな被害を受けた地域の一つである輪島市の行方不明者数は31人から281人に増加した。
地震により輪島市では数十軒の家屋が倒壊し、火災で広い範囲が焼け落ちた。

2024年1月6日、石川県で地震が発生し、救助隊員らが行方不明者の捜索を行っている。(写真:共同通信/VNA)
大雪により救助活動が妨げられ、主に道路の寸断や土砂崩れにより2,300人以上が孤立したままとなっている。 1月8日現在、石川県では約1万8000世帯が依然として停電しており、1月7日時点では6万6100世帯以上が依然として断水状態にある。
約2万8800人が緊急避難所に避難しているが、その多くは電気、水、暖房が不足している。
一方、当局は、場所によっては10センチを超える大雪が降ると家屋の倒壊が増える恐れがあり、雨が何日も続くと土砂崩れの危険性が高まる恐れがあると警告した。
石川県知事の馳浩氏はNHKのインタビューで、政府は災害の影響を乗り越えるために全力を尽くすと語った。
現在、最優先課題は瓦礫の下に閉じ込められた人々を救出し、孤立した地域に到達することだ。政府は孤立した地域に到達するためにヘリコプターと兵士を派遣した。
最近、石川県珠洲市で、倒壊した家に5日間閉じ込められていた90歳の女性が救出された。
1月1日、石川県能登半島とその周辺地域をマグニチュード7.6の地震が襲った。この地震の後には数百回の余震が続いた。気象庁は今回の地震を「令和6年能登半島地震」と正式に命名した。
日本では毎年何百もの地震が発生していますが、40年以上にわたって施行されている厳しい建築規制のおかげで、被害のほとんどは最小限に抑えられています。
しかし、能登のような急速に高齢化が進む地方の地域では、多くの家がかなり昔に建てられたものとなっている。
(出典:vietnamplus)
[広告2]
ソース







![[写真] ファム・ミン・チン首相、ベトナム製品に対する米国の相互関税導入に関する会議を議長](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/5/9b45183755bb47828aa474c1f0e4f741)







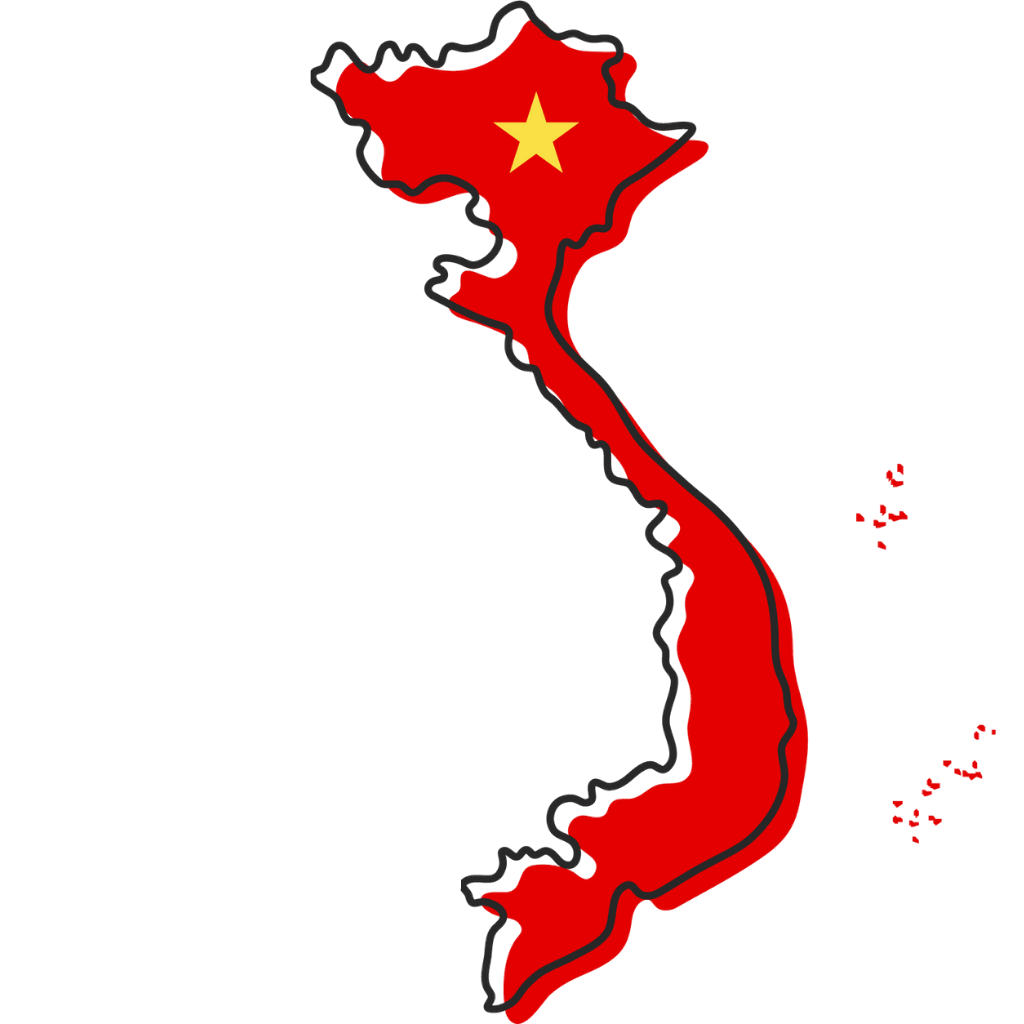
















![[写真] ハノイ、同志カムタイ・シパンドンを偲んで半旗を掲げる](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/5/b73c55d9c0ac4892b251453906ec48eb)

![[写真] ドンナイ省の人々がパレードに参加する部隊を温かく歓迎](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/5/ebec3a1598954e308282dcee7d38bda2)
























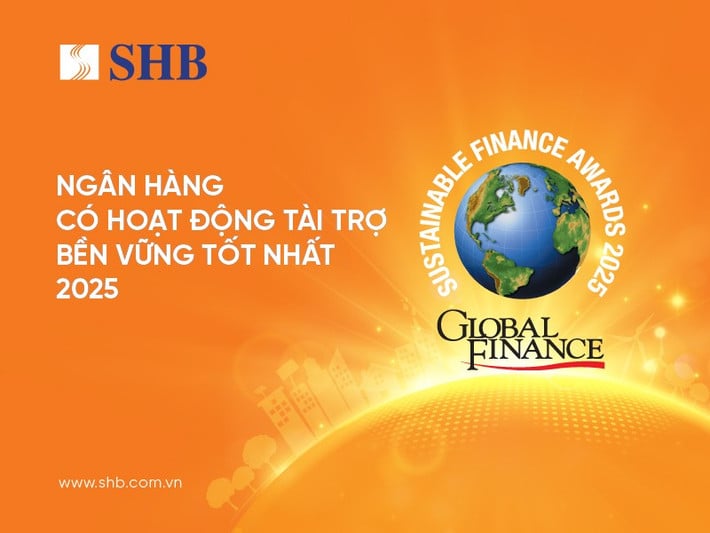











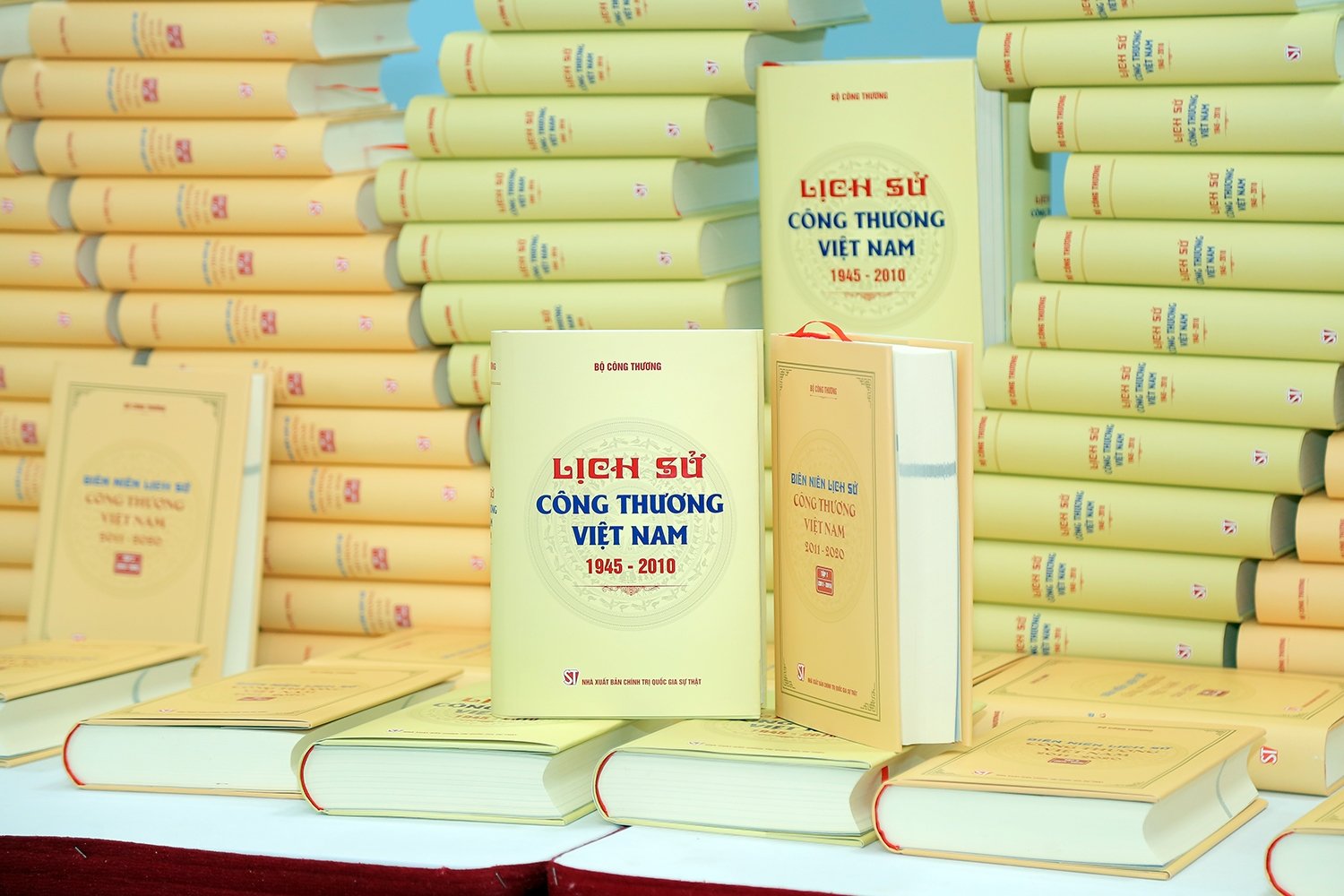
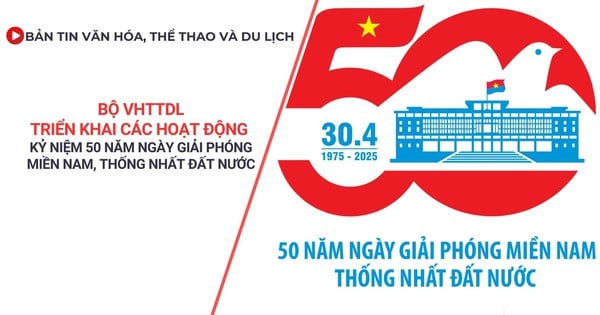






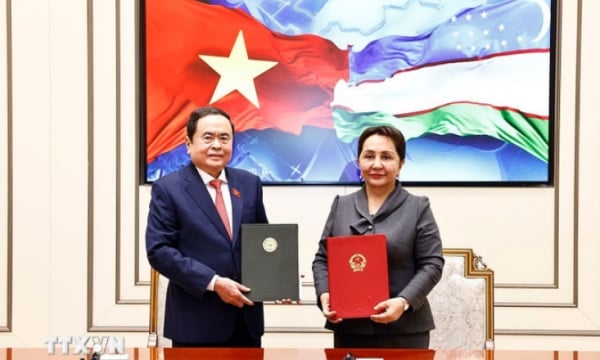












コメント (0)