ロシアが最近、核攻撃の敷居を下げ、抑止力の対象となる国や軍事同盟の範囲を拡大する核ドクトリンの改訂版を承認したことは、各国からさまざまな反応を引き起こしている。
 |
| ロシアの改訂された核政策は国際社会でさまざまな反応を引き起こした。 (出典:ゲッティイメージズ) |
スプートニク通信によると、林芳正官房長官は11月20日、ロシアの核政策が変化する中、ロシアの動向を日本は注視していると述べ、「ロシアは以前、ウクライナ紛争に関連して核兵器の使用を示唆していた」ことを懸念していると指摘した。
「日本は核兵器の被害を受けた唯一の国であり、そのような兵器の脅威はなく、ましてや使用があってはならないと信じている」と林氏は語った。
日本政府関係者によると、日本はこれまであらゆる機会を通じてこうした立場をモスクワに伝えてきたほか、国際社会にも訴えており、「今後もそうしていくつもりだ」という。
一方、フランスのジャン=ノエル・バロ外相は同日、テレビ局フランス2のインタビューで、ロシアのプーチン大統領による核攻撃の閾値を下げる決定は単なる「言葉」であり「我々を脅かすものではない」と強調した。
米国と欧州連合(EU)もロシアの新たな核政策に反応した。
一方、中国は、モスクワの動きを受けてすべての関係国に対し「冷静さと自制を保つ」よう呼びかけ、対話を通じて緊張と戦略的リスクを軽減するために協力すべきだと主張した。
AFP通信は、中国外務省の林建報道官の発言を引用し、北京の立場は依然としてすべての関係者に状況を鎮静化し、政治的手段でウクライナ危機を解決するよう促すというもので、北東アジアの国はこの問題で引き続き建設的な役割を果たしていくと断言していると述べた。
ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は11月19日、同国の最新の核政策である核抑止力分野の国家政策綱領を承認する大統領令に署名した。この教義の基本原則では、核兵器の使用は国家主権を守るための最後の手段であると考えられている。
新たな軍事的脅威とリスクの出現により、ロシアは核兵器の使用条件を明確にする必要に迫られている。具体的には、改訂された教義では、核抑止力の対象となる国家と軍事同盟の範囲が拡大されるとともに、この抑止力によって対抗しようとする軍事的脅威のリストも拡大されている。
さらに、この文書では、ロシアは今後、核保有国が支援する非核保有国によるあらゆる攻撃を共同攻撃とみなすと述べている。
モスクワはまた、自国の主権を脅かす通常攻撃、ロシア領土に対する敵の航空機、ミサイル、ドローンによる大規模攻撃、ロシア国境の侵犯、同盟国ベラルーシへの攻撃に対して核兵器による対抗措置を検討する権利を留保している。
この教義について、クレムリン報道官ドミトリー・ペスコフ氏は同日11月19日、これは「国内だけでなく、おそらく国外でも徹底的な分析を必要とする」非常に重要な文書であると宣言した。
[広告2]
出典: https://baoquocte.vn/nga-tung-hoc-thuyet-hat-nhan-nhat-ban-canh-giac-phap-noi-chang-doa-duoc-chung-toi-294435.html





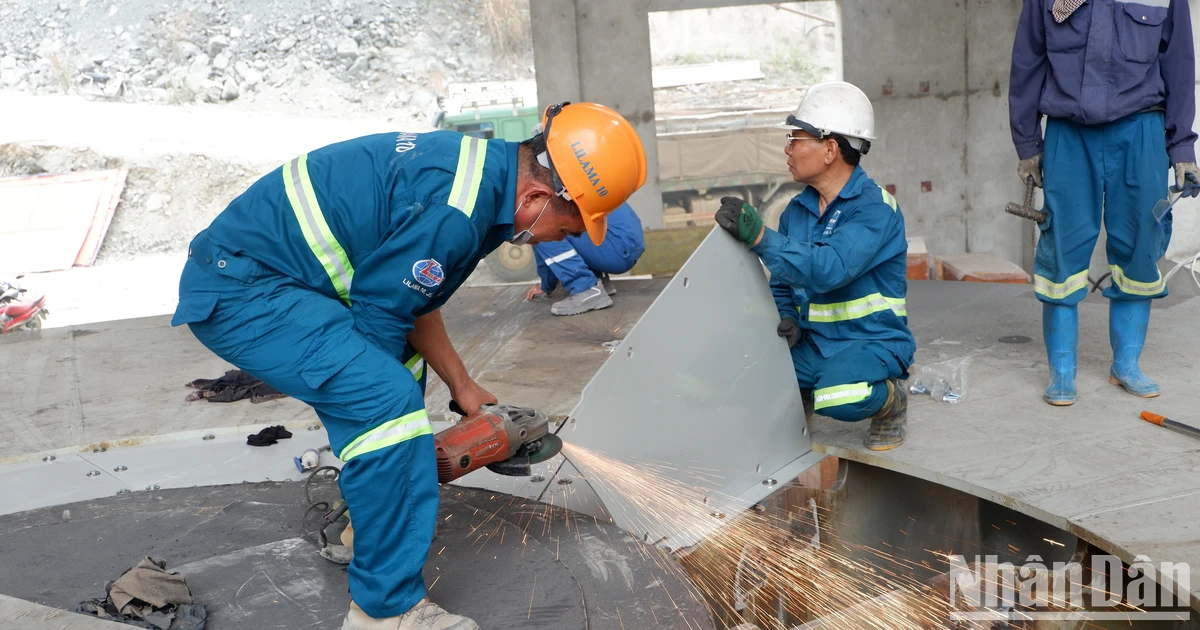




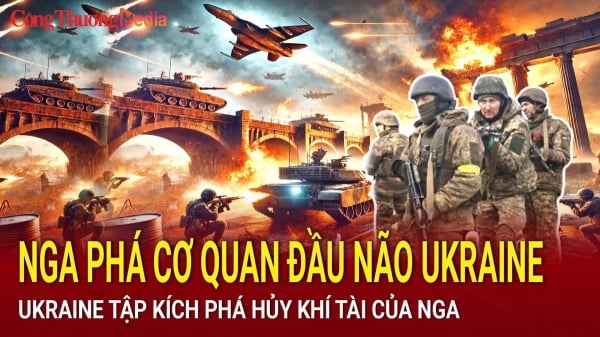







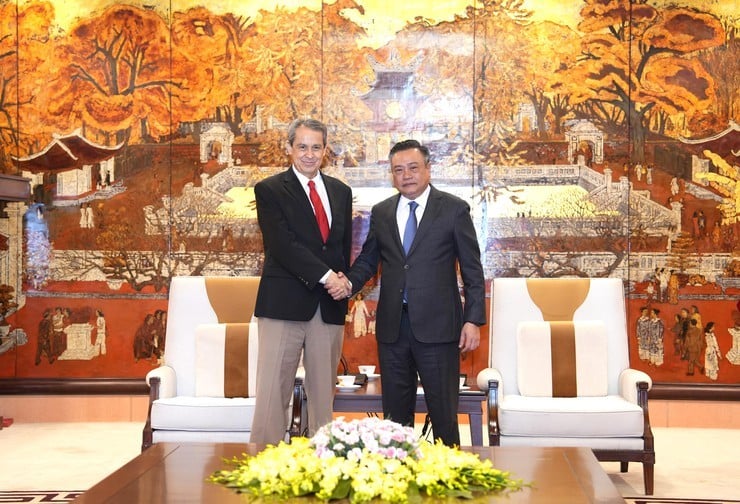

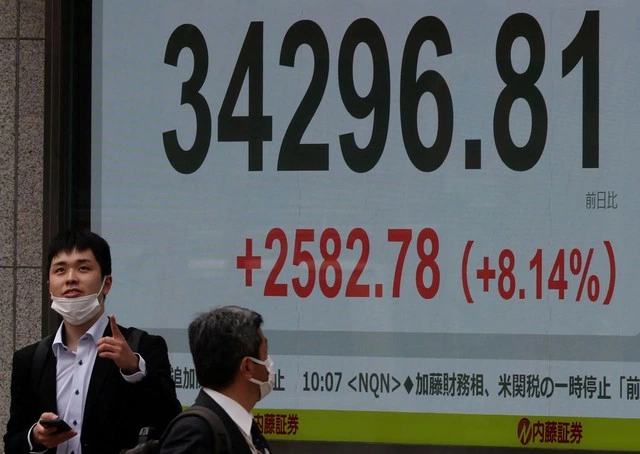















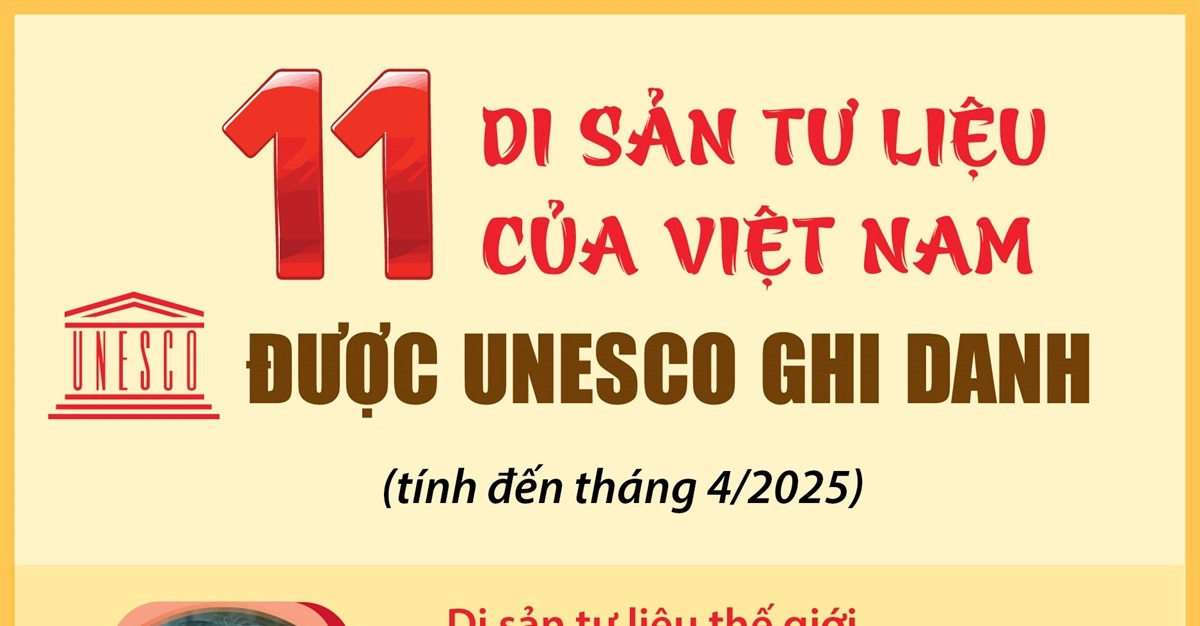



























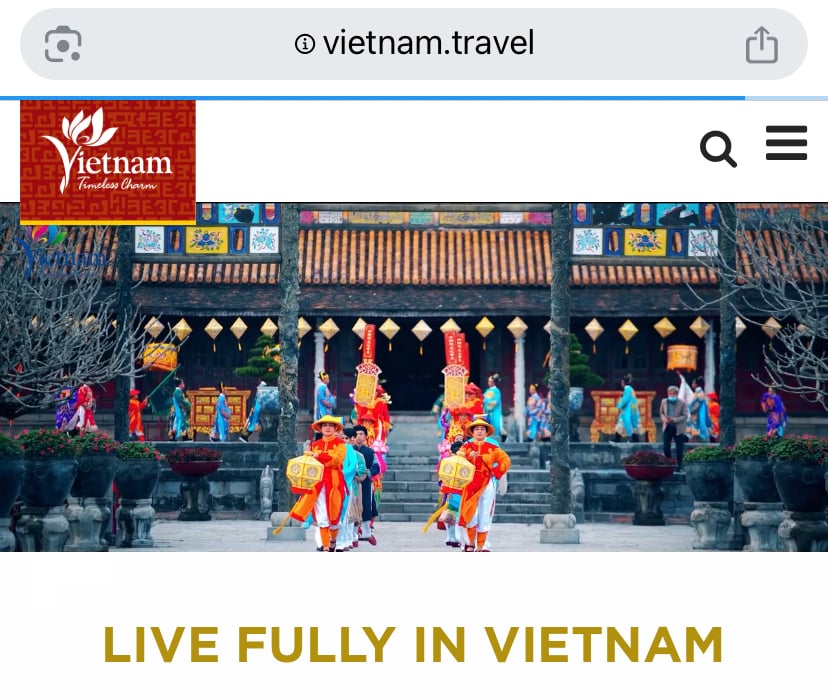































コメント (0)