CPTPP協定以降、アメリカ市場への参入は容易になったが、地理的な距離と言語の壁により、ほとんどのベトナム企業は依然としてこの市場への参入を躊躇している。
困難な時期は終わったが、心配事は残っている。
環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)は2019年1月14日からベトナムで正式に発効し、特にカナダ、メキシコ、ペルーなど南北アメリカ市場とのベトナムの貿易を促進します。
ベトナム繊維協会(VITAS)のヴー・ドゥック・ザン会長は、過去、ベトナムの繊維・アパレル産業がアメリカ市場に参入するのは非常に困難だったと語った。 CPTPP協定のおかげで、繊維・衣料産業はこの市場に参入しやすくなり、カナダとメキシコで高い成長を達成しました。
「私たちは徐々にアメリカ市場に適応しています。以前は、単一の製品ラインの注文を生産したことはなかったが、現在では多くのシャツ工場が、工業生産のベストであっても、単一の注文から年間最大 800 万個の製品の注文を受け付けている。「個別の注文も受け付けています」と Giang 氏は言う。
しかし、機会は課題とも絡み合っています。 VITAS 会長は、アメリカ市場向けに生産・輸出している人たちと同じ懸念を抱いています。
まず、評価基準に対するプレッシャーが大きく、各ブランドが独自の基準を設定しています。次に、支払い遅延のリスクがあります(注文によっては、最大 120 日遅れで支払いを余儀なくされるものもあります)。さらに、リサイクル製品、環境に優しい製品など、持続可能な開発に関連する非常に難しい基準や用語もあります...
ベトナムの繊維・衣料品企業はリスクを抑えるために南北アメリカの買い手との交渉を継続する必要がある。

ベトナム皮革・履物・ハンドバッグ協会(LEFASO)の副会長兼事務局長であるファン・ティ・タン・スアン氏も、皮革・履物業界はCPTPPの機会を活用していると述べた。
カナダ市場は皮革製品や履物に対してかなり「閉鎖的」であり、現在カナダの輸入業者はベトナムからの直接供給を求めている。履物製品は昨年、アメリカ諸国、特にカナダ(40%以上)とメキシコ(50%)への輸出が大きく伸びました。
しかし、シュアン氏は国内の履物企業が直面する大きな課題も指摘した。通常、CPTPP では非常に厳格な原産地証明が求められます。バウチャー制度の透明性を大幅に改善する必要がある。すべての企業がその要件を満たすことができるわけではありません。
一方、ブランドが設定する環境や労働に関する要求事項に加え、各国政府も独自の強制規制を設けており、同じ要求事項に対して複数の工場監査が必要となる状況も発生しており、企業にとって負担となっている。
LEFASO副会長は、ベトナムの中小企業のほとんどは情報とアクセス資源の不足により、CPTPPによるアメリカ市場参入の機会をまだ活用していないと指摘した。
輸出入比率は依然として低い
地理的な距離と言語の壁により、ほとんどのベトナム企業はアメリカ市場、特に一部のラテンアメリカ諸国へのアプローチをためらい、あまり興味を持っていません。
アメリカは大きな市場ですが、ベトナム企業がカナダ、ペルーなどの「ゲートウェイ」市場を活用できれば、市場を多様化する能力が大幅に向上します。
グエン・ホアン・ロン商工副大臣は、近年、ベトナムとアメリカ諸国の協力関係は数々の戦略的コミットメントを通じて強化されてきたが、まだ十分に活用されていない潜在力が多くあると述べた。アメリカに輸出されるベトナム製品の付加価値は依然として低い。アメリカ諸国の輸入構造におけるベトナム製品の割合は依然として限られている。
商工省多国間貿易政策局のゴ・チュン・カン副局長は次のように付け加えた。「カナダ、メキシコ、ペルーを含むアメリカ3カ国への輸出入は、総輸出入額のわずか2%を占めるに過ぎません。」ベトナムは、市場の可能性が非常に大きい国です。
「2019年以来、我々はCPTPP協定の機会を活用してできるだけ早くアメリカ市場に参入することを言及してきました。しかし、ベトナムの企業はまだこの市場に多くのリソースを投入していません。最近、インドネシアはCPTPPへの参加申請を正式に提出した。 「ASEAN諸国に対する我が国の優位性はますます小さくなるだろう」とカーン氏は懸念した。
ベトナムはCPTPP協定を批准した7番目の加盟国である。輪番制によれば、2026年にベトナムがCPTPP理事会の議長の役割を引き継ぐことになる。
「当社はアメリカ市場向けの戦略的かつ重要な輸出製品を保有していますが、市場シェアはまだ小さいです。カーン氏は「どの事業・産業を振興する必要があるかを特定し、それを振興するための政策を策定し、問題が生じれば対処する必要がある」と勧告した。
[広告2]
出典: https://vietnamnet.vn/doanh-nghiep-viet-dung-ngai-vao-thi-truong-chau-my-2366754.html


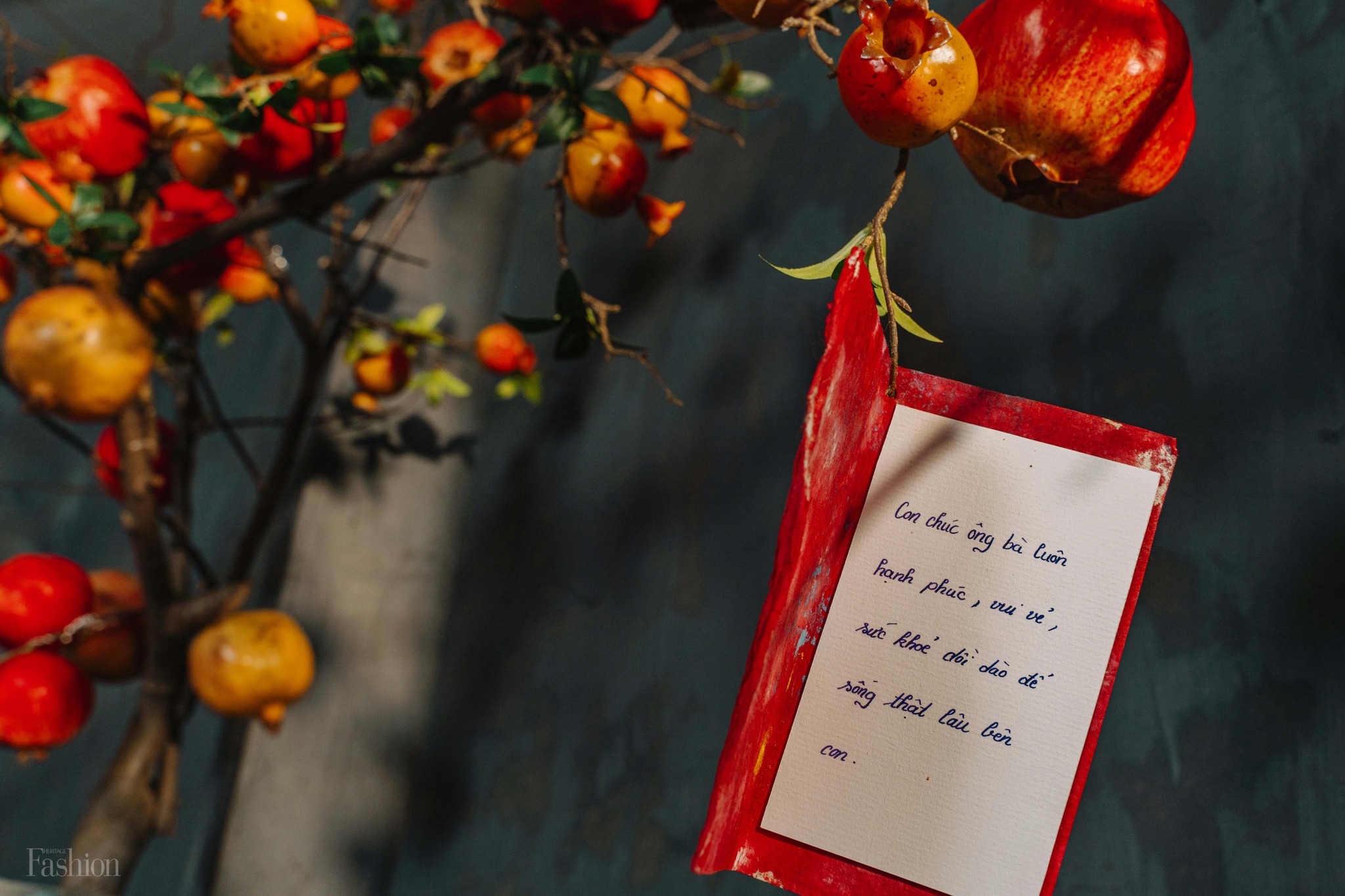




















































コメント (0)