
日本銀行は政策声明で、短期金利をマイナス0.1%に維持し、10年国債の利回りをゼロに制限すると発表した。
日銀の今回の行動はこれまでの予想とほぼ一致している。日本銀行は来週金曜日に記者会見を開く予定で、上田一男総裁がより具体的な指針を示す可能性がある。
日本銀行は声明で、「内外の経済や金融市場を巡る不確実性が極めて高い状況を踏まえ、経済・物価・金融情勢の動向に機動的に対応しながら、粘り強く金融緩和を継続していく」と述べた。
しかし、金融緩和政策によって日銀は例外となった。世界中の主要中央銀行はインフレを抑制するために過去2年間金利を引き上げざるを得なかった。
日銀の決定を受けて円は約0.4%下落し、1ドル=148.16円となった。 10年国債の利回りはほぼ変わらなかった。円は今年に入ってからドルに対して11%以上下落している。
7月の前回の金融政策決定会合で、上田総裁率いる日銀はイールドカーブ・コントロール(YCC)を緩和し、長期金利の変動を容認した。これは、日銀が金利を目標に設定し、必要に応じて債券を売買できるようにする政策手段です。 YCCに対する規制緩和は、黒田前総裁の旧政策からの段階的な脱却の第一歩でもある。
専門家は、日銀が2024年前半頃に金融緩和政策から早期に脱却すると予想している。上田氏自身も、日銀は今年末までにマイナス金利の解除時期を判断するのに十分なデータを得る可能性があると明らかにした。
コアインフレ率は日本銀行が示した2%の目標を17カ月連続で上回っているものの、日銀当局は景気刺激策の解除に慎重な姿勢を保っている。
日本の8月のコアインフレ率は前年同月比3.1%だった。エネルギーと生鮮食品を除いた消費者物価は4.3%上昇した。
イーストスプリング・インベストメンツのエコノミスト、オリバー・リー氏は「日本はデフレ環境から持続的なインフレ環境に移行する可能性が高い」と述べた。
「鍵となるのは賃金です。日本が消費者心理に影響を与えるには、実質的かつ持続的な賃金上昇が必要です。これがプラスの経済成長サイクルの始まりとなることを期待しますが、成功するかどうかはまだ分かりません。状況がどうなるかを見極めるには、おそらくあと6~12ヶ月かかるでしょう」とリー氏は付け加えた。
時期尚早な利上げは経済成長を阻害する恐れがあり、一方、利上げが遅れすぎると円にさらなる圧力がかかり、金融ストレスが増すことになる。
日本の4~6月期の国内総生産(GDP)成長率は、設備投資の低迷により、当初の6%から年率4.8%に下方修正された。
[広告2]
ソース




![[写真] 政治局決議第66-NQ/TW号および第68-NQ/TW号の普及と実施のための全国会議](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/18/adf666b9303a4213998b395b05234b6a)

























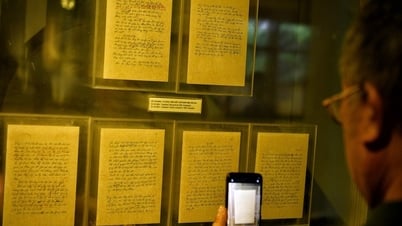
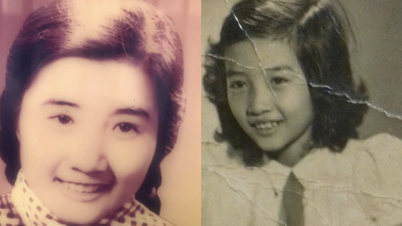




![[写真] ファム・ミン・チン首相が科学技術発展に関する会議を議長として開催](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/17/ae80dd74c384439789b12013c738a045)



















































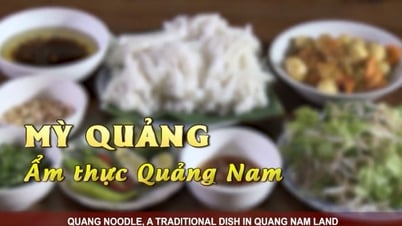







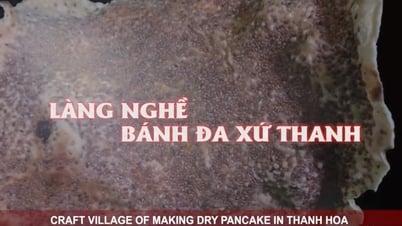

コメント (0)