ロック・トロイ・グループの会長、フイン・ヴァン・トン氏が、この問題について記者や報道陣のインタビューに応じた。
2023年には、同国の米輸出量は810万トン、輸出額は47億ドルに達し、ベトナムの米産業としては記録的な額となるだろう。この数字についてどう思いますか?
2023年に達成される成果といえば、米の価格が上昇して売れやすくなり、米農家の収益が増加することです。これは農家だけでなく社会全体の願いです。
 |
| ハウザン省の農民が米を収穫する |
さらに、国の地位も、米の地位も、農民の地位も向上します。ベトナムの米産業は、価格交渉権を買い手から売り手へと徐々に移行させてきた。
2023年には、需給、気候変動、サプライチェーンの混乱、そして特に消費者心理といった要因により、ベトナム米は正当な地位を取り戻したと言えるでしょう。
ベトナム米の地位維持はよく話題になる話だ。解決策は何だと思いますか?
「2030年までにメコンデルタ地域でグリーン成長を伴う高品質かつ低排出の稲作100万ヘクタールの持続的開発」プロジェクトは、バリューチェーンに従って生産システムを再編し、持続可能な農業プロセスを適用して価値を高め、稲作産業の持続的開発、生産と経営の効率、稲作農家の収入と生活の向上、環境の保護、気候変動への適応、温室効果ガスの排出削減などの課題を提起し、ベトナムの国際公約の実施に貢献します。
 |
| ロック・トロイ・グループ会長、フイン・ヴァン・トン氏 |
インフラ投資に伴う生産指向は、各輸出市場向けの栽培地域、米の品種からの特定の計画と関連しており、そこでは標準的な生産プロセスがあり、バイヤーも私たちのプロセスを受け入れていることがわかります。したがって、ベトナムの米産業は現在の地位を完全に維持することができます。
特に、持続可能な米の連鎖に沿って要素を集め、米産業のエコシステムを組織することは、社会資源を最大化し、要素間の不必要な利益相反を解決し、互いの競争を回避する方法である。これが実現できれば、豊作なのに価格が低いという状況に終止符を打つことができます。
最近、ベトナム米は世界一と称され続けています。特に、米産業の輸出活動を支援するための足がかりを作るという点において、このことに対してどのような評価をされますか。
我が国が米輸出国と異なるのは、米の品種が自然選択されており、収穫量が単一であるという点です。ベトナムでは、科学者たちが短期間で高収量の品種を作り出した。ベトナムは、環境、自然、気候、土壌のおかげで、年間を通じて継続的に多くの作物を生産することができます。これはベトナムが世界の食糧安全保障に貢献し、国内の食糧安全保障を確保するための要因です。
国家ブランド、企業ブランドを構築し、価格交渉力を獲得し、それによって農家の収入と地位を向上させ、生産と環境保護を結び付け、田舎をより住みやすい場所にする...私たちは、生産の再編成を改善することで、ベトナムの米産業が新たな章に入ると信じています。
しかし、米産業を多角的に見る必要もあります。たとえば、他の作物に比べて農家の収入が増加します。
100万ヘクタールの高品質米プロジェクトは非常に良いですが、収入が他の作物より高くなければ、農家を奨励することは難しいでしょう。副産物を付加価値に変えることで稲作農家の収入問題を解決します。これにより、農家は他の作物と同等かそれ以上の利益を得ることができるようになります。
例えば、4,300万トンの米があれば、500万トンの籾殻を集めることは十分可能です。 500万トンの籾殻を廃棄パネルに加工することで、完全に生分解性の天然ポリマー製品が生まれ、環境問題が解決され、500~520億ドルの売上高と、現在の米輸出額に匹敵する30~40億ドルの利益がもたらされます。
もちろん、この数字を達成するには、市場の問題や技術設備など、やるべきことがまだたくさんあります。しかし、製造された製品は幻想ではなく、実際にノルウェーの注文に応じて輸出された製品もあるため、これは実現可能な数字です。
米からは、籾殻以外にもぬかや砕米などの廃棄物も出ますが、これらはすべて大きな付加価値をもたらす可能性があります。これは、農家の所得利益と負担のバランスの問題を解決するための方向性です。それから、食糧安全保障の話はそれほど心配していないんですが、米農家の収入は高くないんです。特に、当社は加工技術を習得しているため、この目標は完全に達成可能です。
ありがとう!
| 2023年の米の輸出量は810万トン、金額にして47億ドルに達し、2022年と比較して量で14%、金額で35%増加する見込みです。米業界は世界市場に参入して34年を経て、量と売上高の両方で輸出記録を樹立しました。 2023年の米の平均輸出価格は1トンあたり580ドルに達し、2022年に比べて19%増加する見込みです。 |
[広告2]
ソースリンク





![[写真] ファム・ミン・チン首相が科学技術発展に関する会議を議長として開催](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/17/ae80dd74c384439789b12013c738a045)
![[写真] 政治局決議第66-NQ/TW号および第68-NQ/TW号の普及と実施のための全国会議](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/18/adf666b9303a4213998b395b05234b6a)

























![[写真] ニャンダン新聞社でホーチミン主席生誕135周年を記念した写真展を訪れ、特別号を受け取るために列を作る読者たち](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/17/85b3197fc6bd43e6a9ee4db15101005b)












































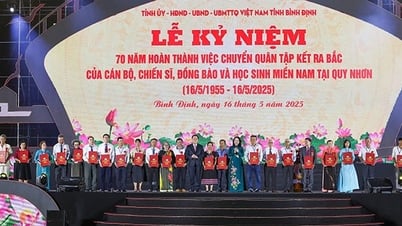










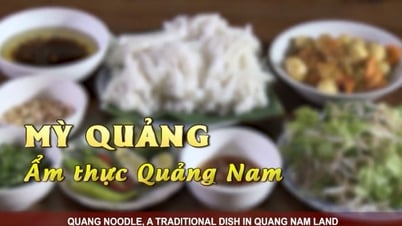





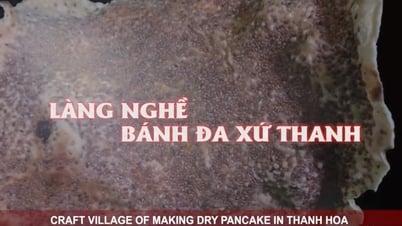


コメント (0)