
今回国会に提出された社会保険法案(改正案)の中で、多くの議員が関心を持ち、意見が分かれているのは、年金受給年齢に達しておらず、社会保険を継続して納付しておらず、20年間社会保険を納付しておらず、社会保険の一時受給を希望する場合の一時受給条件に関する規定である。
したがって、社会保険法案第74条と第107条には、国会が議論すべき2つの選択肢がある。オプション 1 では、従業員が 2 つのグループに分けられます。グループ 1 は、従業員の一時社会保険加入政策の実施に関する国会の 2015 年 6 月 22 日付決議第 93/2015/QH13 号で規定されている一時社会保険加入条件を引き続き適用します。つまり、この法律が発効する前 (2025 年 7 月 1 日予定) に社会保険に加入していた従業員は、12 か月後には強制社会保険の対象にならず、任意社会保険にも加入しません。第2群、すなわち、本法の発効日以降に社会保険に加入し始める従業員は、一時的社会保険給付の受給条件として、この規定の対象とはなりません。一方、オプション 2 では、従業員が年金および死亡基金に拠出した合計時間の 50% を超えない範囲で部分的に解決されることが規定されています。従業員が引き続き社会保険に加入し、社会保険の給付を享受できるように、残りの社会保険納付期間が確保されます。
国会常任委員会は、国会への受理と説明に関する報告書の中で、政府が提出した2つの選択肢は最適ではなく、一時的な社会保険給付を受ける状況を完全に解決して高いコンセンサスを生み出せない可能性があるものの、これらが有力な選択肢であり、特に選択肢1にはより多くの利点があると述べた。討論会では、多くの代表者が選択肢 1 に同意し、選択肢 2 を支持する意見が多くありました。
ファン・タイ・ビン代表(クアンナム省国会議員代表)は、彼の前で議論された意見に同意せず、討論を要求し、議長によって承認された。
ファン・タイ・ビン代表は自身の意見を述べ、国会常任委員会が提案した2つの選択肢はそれぞれ利点と限界があり、最適な選択肢ではないと述べた。これら 2 つの選択肢の最大の違いは、従業員が社会保険に加入する時期が法律の施行前か後かという点です。 2025年7月1日(法律施行予定日)までに保険料を納付すれば、社会保険の給付を1回だけ受け取れます。この日以降は撤退できません。
代表者は、社会保険を一時脱退する必要性は、この法律の発効前か発効後かを問わず、従業員の正当かつ合理的な権利であると強調した。したがって、2 つの選択肢の利点を最大限に活かすとともに、その限界を克服するために、ファン・タイ・ビン代表は、法案の 2 つの選択肢を 1 つの新しい選択肢に統合して、労働者の権利という当面の問題を解決し、長期的には、まず第一に、貢献と利益の原則を確保し、国家、企業、労働者の利益を調和させながら、労働者の権利を最優先するという精神で社会保障を確保するという問題を解決することを提案した。したがって、この法律の施行日前に支払った場合と施行日後に支払った場合を区別せずに、一時的な社会保険を受け取ることを提案します。特別な困難、重病、海外移住などの場合には、支払った社会保険料の全額を一括で引き出せるように規定すべきである。残りのケースでは、従業員の給与から従業員が直接支払った金額(8%)のみを引き出すことができます。雇用主が支払った残りの金額は、従業員が後で年金を受け取ることができるように保持されます。
ファン・タイ・ビン議員は議論の最後に、国会常任委員会と起草委員会は、提案された選択肢を検討し、受け入れ、国会代表者と協議して、一時的な社会保険給付の受給に関する規制について3つの最も適切な選択肢の1つを選択することを検討すべきだと提案した。
また、この討論会で、ファン・タイ・ビン代表は、社会保険の故意の支払い遅延や支払い逃れのケースを扱う法案の規定は、罰則レベルが低いため抑止力が十分ではないと述べた。企業が社会保険資金を故意に流用する事態を回避するために、社会保険料の滞納額や脱税額の支払いに加え、国立銀行が定める延滞金利に相当する罰金を計算することを推奨します。
労働組合の権利と責任に関しては、代表者は労働組合の訴訟権に関する規定に同意した。しかし、現状の問題は、労働組合が訴訟を起こすためのプロセスと手順が非常に難しく、特に、訴訟される前に従業員と企業の認可に関する規制を検査、監査し、行政違反を処理しなければならないことです。労働組合の監督や検査を通じて請願したが企業が故意に従わない場合に、労働組合組織が訴訟を起こしやすくするための具体的な規定を法律に提案する。訴訟を起こすために行政処分を受ける必要はありません。
会議の議題によれば、国会は5月27日一日中、社会保険法案(改正案)について議論し、6月25日のこの会議で可決することに合意する。
ソース




![[写真] 党と国家の指導者が特別芸術プログラム「あなたはホーチミンです」に出席](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/18/6895913f94fd4c51aa4564ab14c3f250)
![[写真] ホーチミン主席生誕135周年を祝う特別国旗掲揚式](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/19/1c5ec80249cc4ef3a5226e366e7e58f1)

![[写真] 党と国家の指導者がホーチミン主席廟を訪問](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/19/d7e02f242af84752902b22a7208674ac)


















































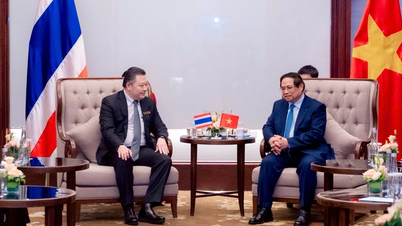






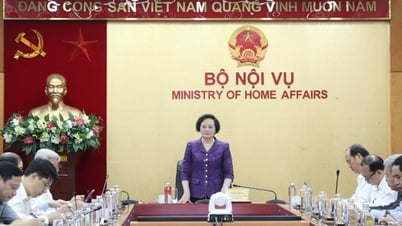























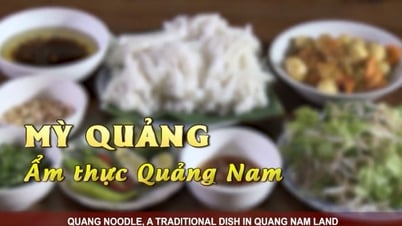




コメント (0)